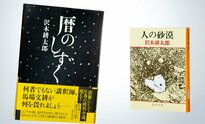首都圏で中学受験をする小学生の割合は約5人に1人となり、東京23区ではおよそ半数が国立・私立中学へ進学する地域もある。中学受験の過熱にともない、教育虐待などネガティブな側面がクローズアップされることもある一方で、たとえ第1志望に合格できなくても「やってよかった」と振り返る親子もいる。その“差”はどこにあるのか。
【写真】「中学受験」をテーマにした“話題作”を出版した人気作家はこちら
* * *
2015年以降、中学受験する子どもの数は増加の一途を辿り、2023年には首都圏で約5万2600人とピークとなった(首都圏模試センター調べ)。直近の2年はそれぞれ前年より100人ほど微減しているが、25年も約5万2300人と高止まりの状態が続いている。25年の首都圏受験率は18.1%となり、同調査開始以来、2番目に高い受験率となった。
森上教育研究所代表の森上展安氏は「受験者層のすそ野が広がっている」と話す。
「受験者の全体数が微減したといっても、東京・神奈川入試が始まる2月1日午前の私立受験率は15.2%で、23年よりも0.2ポイント上がっています。いまだ“過熱状態”は続いていると言えるでしょう。特に偏差値45~54の中間層は倍率が高くなっており、共学、別学でならすと実倍率は2・5倍を超えています。必ずしも偏差値の高い難関校を目指す家庭ばかりではなくなってきています」
こうした世の中の流れを受け、中学受験をテーマにした漫画や小説の刊行も相次ぐ。
小学生が挑戦する中学受験はその負荷が大きいこともあり、家庭の崩壊や教育虐待などネガティブな側面が描かれることも多い。だが、作家の早見和真さんが今年3月に出版した新作『問題。 以下の文章を読んで、家族の幸せの形を答えなさい』(朝日新聞出版)は、少し趣が異なる。
主人公は、志望校をなかなか見つけられずにいる小学6年の十和(とわ)。娘に受験を勧めたものの、一向に口を出す気配のない母、娘の特性を深く理解し、並走することを決めた父、そして父の人となりに尊敬の念を抱く塾講師などが、受験への肯定感と優しさをもって描かれ、受験に向かう家族の半年間の物語がつづられている。