


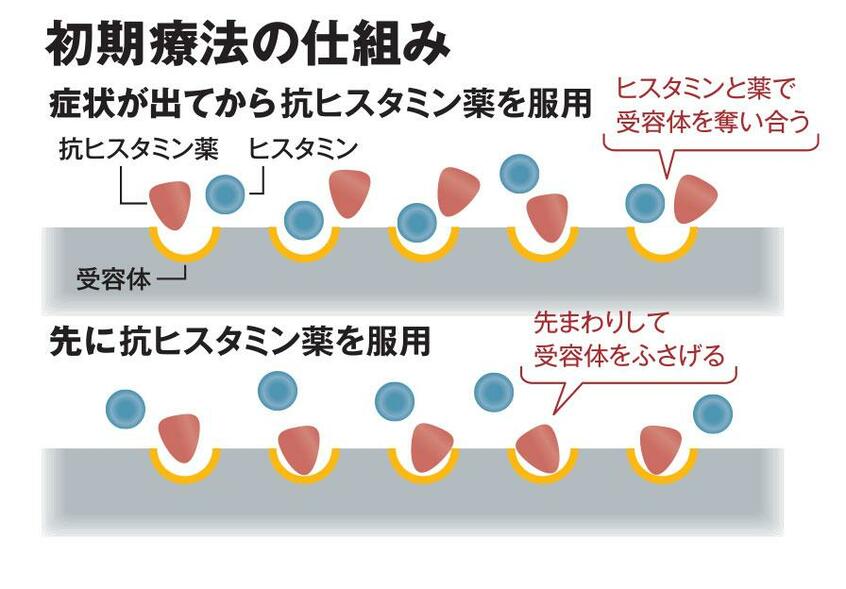
今や日本人の4人に1人が発症する「国民病」とも言われる花粉症。その被害の深刻さ、広範さは、もはや自然災害の一つといっても過言ではない。だから対策も災害レベルで考えたい。AERA 2019年11月25日号では、「花粉症タイムライン」を特集した。
【図解】ベストなタイミングで対策を!「花粉症タイムライン」はこちら
* * *
アレルギー疾患のエキスパートで、花粉症治療の先駆者である日本医科大学の大久保公裕教授(60)は、専門医を受診するのは「11月がベスト」と言う。
「花粉が飛ぶ季節が近づくほど、治療の選択肢が狭まってしまいます。自分がどんな治療法を選択したいのか、専門医に相談して今のうちに治療方針を立てるのがよいでしょう」
とりわけ今春、薬の服用だけでは十分な効果が得られず、仕事や生活に支障が出るほど花粉症に苦しんだ人は、来シーズンに向けた治療開始のタイミングを逃さないよう注意が必要だ。大久保教授は言う。
「花粉の飛散が植物の生体運動であることを考えれば、花粉症は一種の自然災害です。自然の働きに対して事前に予想を立てるのは困難ですが、最悪の状況をイメージして被害を最小限に食い止めるのが大事です」
アエラは今回、花粉症を災害の一つと捉え、被害を最小限に食い止め、できることならば完全に逃れるための「タイムライン」を作成した。11月、12月、1月、2月、そして本番の3月。それぞれのタイミングでベストの対策をとることで、来年の花粉症との闘いで被害を受けないことが最終目標だ。
それでは、タイムラインを順に追っていこう。
現在、事前に花粉症に備えられる治療法は、3種に大別される。1日1回、スギ花粉の抗原エキスを舌の下に1~2分間入れてから飲み込む「舌下免疫療法」。レーザーで鼻の粘膜を一時的に凝固させる「レーザー療法」。さらに来シーズンに向けて健康保険適用が始まる見込みの「抗体療法」だ。厚生労働省の専門家部会は10月31日に重症の花粉症患者の治療薬として、抗IgE抗体製剤「ゾレア」(一般名:オマリズマブ)を了承。近く正式承認されることが内定した。従来の治療法では効き目が不十分だった重症患者にも効果が期待できる。





































