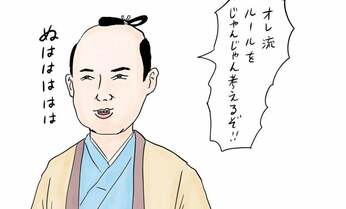「歴史」に関する記事一覧


「麒麟がくる」で“見たことのない信長”を生み出した染谷将太は、クライマックス本能寺の変で何を見せるのか?
2月7日(日)の最終回に向けて、ますます盛り上がりをみせているNHK大河ドラマ「麒麟がくる」。その中で織田信長役を演じている染谷将太さんは、「革新的な織田信長像をゼロから構築したい」とのオファーを受けて引き受けたという。一年以上をかけて濃密な一人の人生を演じ切るのは、初めての経験だったという。撮影現場で制作陣と日々奮闘し、新たな挑戦をしている染谷さんに、『歴史道vol.13「本能寺の変と光秀の最期」』(週刊朝日MOOK/朝日新聞出版)で信長に対する思いを語ってもらった。特別に全文公開する。



秀吉や家康が「キリスト教の布教」を認めていたら日本はどうなっていたのか?
アメリカ・ヨーロッパ・中東・インドなど世界で活躍するビジネスパーソンには、現地の人々と正しくコミュニケーションするための「宗教の知識」が必要だ。しかし、日本人ビジネスパーソンが十分な宗教の知識を持っているとは言えず、自分では知らないうちに失敗を重ねていることも多いという。また、教養を磨きたい人にとっても、「教養の土台」である宗教の知識は欠かせない。西欧の音楽、美術、文学の多くは、キリスト教を普及させ、いかに人々を啓蒙するか、キリスト教を社会にいかに受け入れさせるのかといった葛藤の歴史と深く結びついているからだ。世界94ヵ国で学んだ元外交官・山中俊之氏による著書、『ビジネスエリートの必須教養 世界5大宗教入門』(ダイヤモンド社)の内容から、ビジネスパーソンが世界で戦うために欠かせない宗教の知識をお伝えする。

特集special feature





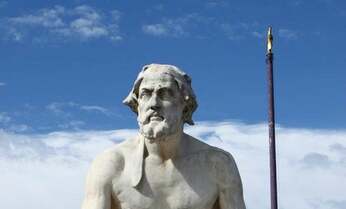
古代ギリシア「アテナイ」没落にみる流行病とデマ、私利私欲…現代の医師が解説
筆者の愛読する古典のひとつに、トゥキディデス(紀元前460年頃-紀元前395年)の『戦史』がある。もっともギリシア語は大学生時代、アリストテレス全集を翻訳された島崎三郎先生という大家に師事しながら3カ月で挫折し、希英対訳ローブの英語ページと岩波文庫の日本語訳版で読んだだけである。しかし、翻訳でも、国際間の緊張と駆け引き、国益よりも国民の受けを狙ったタカ派のポピュリスト政治家や、やたらに威勢の良い軍人、勝利のためには政治体制の異なる大国ペルシアから海軍を導入するスパルタ王など、人間と政争の本質は今もほとんど変わっていない。実際、欧米では、政治家や軍人を志す若者にヘロドトス『歴史』と並んで、トゥキディデスは必読の書なのだそうである。