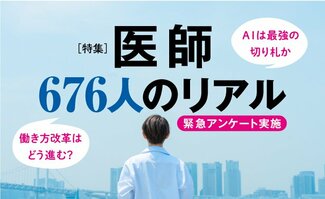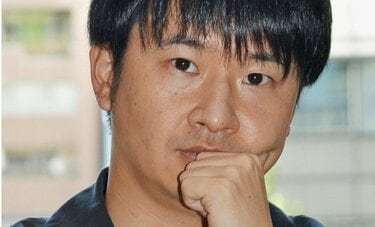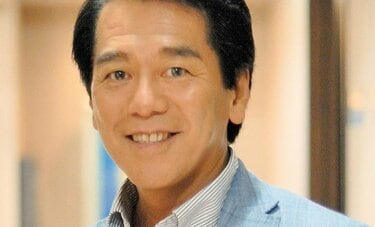顔面「グーパンチ」殴られるのは逃げ場のないホテルや車内 DV被害の相談3割が男性
(写真:Getty Images)
配偶者らパートナーからのDV被害を訴える男性が増加している。昨年、警察に相談や通報をした男性は全体の約3割だった。AERA 2024年6月10日号より。
* * *
「人に殴られるという滅多にない経験を、好きだった人にされたのは死ぬまで忘れられないと思います」
こう打ち明ける東京都の20代の会社員男性は、昨年夏まで約半年間交際した20代女性に繰り返し暴力を受けていた。
付き合い始めて数カ月後。「アルバイト先から給与が支払われない」と言う彼女のために家賃やサブスクの費用を肩代わりするようになった。その額は数カ月で数十万円に。女性は「お金がない」と言いながら整形手術をするなど浪費癖があった。男性が「もう少し出費を抑えたほうがいいんじゃない」と諭すと、女性は急に不機嫌になり、「グーパンチ」でいきなり顔面を殴ってきた。腕で顔を覆ってパンチを防ごうとすると、爪で引っかかれた。
殴られるのは逃げ場のないホテルや車内。さすがに無抵抗の相手を殴り続けるのは心が痛んで途中でやめるはずだと考え、「そんなに怒りが抑えられないんだったら、殴りたいだけ殴ってみろ」と言ったこともある。すると、全く容赦なく30発以上殴られ続けた。「この人は暴力をふるうことに全く良心の呵責がないんだ」。そう思い知り、金銭の問題も含めてこれ以上付き合うのは無理と悟った。別れ話を切り出すと女性は逆上し、「殺す」と言ってのしかかり、腕で首を絞めてきた。女性は華奢だが長身で腕をふりほどくのも、やっとの思いだった。身の危険を感じる局面でも、男性は一度も女性に暴力をふるわなかったという。正当防衛だと主張しても、やり返すとこちらがDV加害者に仕立てられかねない、と考えたからだ。しかし、身体的な痛みよりもつらかったのは、精神的ショックだったという。
「私自身、人を殴ったことはありません。人を殴る、という行為にはしる気持ちがそもそも理解できません。殴られている時は、どう受け止めていいのか分からない混乱状態に見舞われていました」
余程のことがなければ人は人を殴ったりしないはずだ。彼女を激高させるほどの落ち度が自分の側にあったのか。こうなる前に、なぜ自分は何とかできなかったのか。男性は殴られながら自問を繰り返したという。
AERA 2024年6月10日号より
周囲の反応も男性を苦しめた。「相手がヒステリックになっただけでしょ」「男なんだから、少し殴られたぐらい平気でしょ」。親身になってくれる人はいなかった。
「男の側が被害を受けたと言っても、大したことじゃないと思われるんです。友人からは、『結果的に別れられたからよかったじゃん』とも言われました。そういうことじゃないんだけどなって……」
言葉の暴力もあったが、ほとんどが身体的な暴力だった。女性は親と仲が悪く、つかみ合いのけんかをしたこともある、と語っていた。「沸点に達した感情を表す手段として、暴力が体内にインプットされてしまった人」。そんな印象が強く残ったという。
男性は彼女と別れた今も、殴られたシーンが不意によみがえることがある。
相談できぬ男性なお
「転職して東京で暮らすようになったのも、彼女の近くにいたいと思ったからでした。仕事の調子が悪い時、自分はなぜいま東京にいるんだろう、あんな暴力をふるう人間のためにかけがえのない人生の進路を変えられてしまった、もしかすると人生を棒に振ったんじゃないかと、とことん悪い方向に考えてしまうことがあります」
警察庁によると、パートナーからDV被害を受け、警察に相談や通報をした男性は2023年に2万6175人で全体の29.5%。女性の方が多い状況だが、13年に3281人(6.6%)だった男性被害者は18年には1万5964人(20.6%)と増加傾向にある。男性が被害を訴えやすい環境に変化しつつあるものの、「男だから」というジェンダー意識も相まって、DV被害を周囲に相談できない男性は依然として多いとみられている。
一方、加害の記憶に苦しむ女性もいる。東日本在住の看護師の50代女性は、アエラのアンケートにこんな言葉で始まる回答を寄せた。
「元夫が働かず、クズのような人でした」
修羅場は約10年前。2人の息子は当時、高校生と大学生。教育費がピークにさしかかっていた。住宅ローンも抱え、お金が最も必要な時期に「働かない夫」のために家計は突如、火の車になった。女性は2カ所の病院を掛け持ち勤務し、その合間に、入院した義父の世話もした。
働かぬ夫に怒り
「その時の気持ちはこっちが正義で、夫が悪。悪なんだから(夫は)懲らしめられて当然という感覚でした」
気づけば、日常的に夫を罵倒し、殴る蹴るの暴力を止められなくなっていた。
「夫がひきこもりにならず、働き続けてさえいてくれれば、私も夫もDVにかかわるような人生を送ることがない人間だったと思います」
虐待などのトラウマ経験のない女性がなぜ、DVの加害者になってしまったのか。事情を尋ねると、女性は罪悪感と後悔を口にしながら経緯を吐露した。
夫は新卒で大企業の研究職に就職。海外勤務も経験したエリート社員だった。感情をあまり表に出さず、まじめでおとなしいタイプ。喜怒哀楽がはっきりしていて感情の起伏が激しい女性とは対照的な性格だという。難点は「転職癖」。52歳までに官公庁を含め転職を7回繰り返した。理由はさまざまだった。
「上司と合わない」「仕事のレベルが低すぎる」「忙しい割に待遇が悪い」
どれも腑に落ちなかった。転職先が決まる前に辞職する場当たり的な行動も解せなかった。しかし女性は、正面から夫を問いただすことはしなかったという。
「若い頃は転職を繰り返すことがチャレンジ精神のようにも見えたし、高給を維持できる研究職の転職先がスムーズに見つかっていたこともあって目をつむることができました」
でも、と女性はこう続けた。「今思うと、夫に対する怒りや不信をずっと抱えていたのだと思います。DVをするようになって、私は許していなかったんだ、と自覚しました」
「動物以下じゃん」
「堪忍袋の緒が切れた」のは夫が52歳の時。「その年齢だと絶対に次の職場を確保できない」と諭す妻子の制止を振り切って辞職した夫は案の定、転職先を見つけられなかった。
「それ見たことかと。ぜいたくなんて言ってられない状況なのに、夫は『まともな仕事がない』と、そのままずるずると働かなくなり、自宅にひきこもるようになりました」
これを機に女性のDVが始まる。一方的に夫を怒鳴る日々が1年余り続いた。
ハローワークで仕事を探すよう促しても、「ろくな仕事はない」と拒む夫の背中を拳骨で叩きながら、「なに言ってんの!」と声を上げた。自宅にいてもほとんど家事をしない夫に「せめて買い物ぐらいして」と訴えると、「平日の昼間に外をぶらぶらしていると無職だと近所の人にばれる」とメンツを気にする夫にさらに苛立ちが募り、「そんなこと言ってる場合じゃないだろ!」と蹴飛ばした。
そして、「鳥や獣だって、巣立ちするまで子どもの世話をするのに、こうやって働かなくなったあんたは動物以下じゃん」と罵った。職場から帰宅し、「あー疲れた」とつぶやく女性に、「そんなに疲れるなら仕事やめて、みんなで生活保護を受ければ楽だよ」と返す夫にカチンときて、「ふざけんじゃないよ!」と罵声を浴びせた。
「言い返されると、怒りが増幅するんです」
別の部屋で寝ている夫のいびきも許せない。
「こっちが眠れないほど家計のことで苦しんでいるのに、いびきなんかかきやがって」
寝ている夫の枕元に詰め寄り、「うるさい! なに、いびきかいてんだよ。こっちは明日も仕事があんのに!」と怒鳴りつけたこともある。
夫は何を言われても、ただ黙っていた。蹴られても叩かれてもやり返さず、時折、「やめて」と言うぐらい。その反応も女性には気に食わない。
「やめてほしかったら働け!」
長男は大学院進学を断念して就職。東大受験を予定していた次男には「下宿代を捻出できない」と説得し、自宅から通える国立大学に志望先を変更してもらった。女性は息子たちとともに、夫に「出てけ!」と繰り返すようになった。夫は強く拒んだが、実家に追い出す形で別居。3年後に離婚が成立した。
「夫は今も実家でひきこもりの生活をしていると思います」
そう話した後、女性は少ししんみりしてこう言った。
「私と息子の3人が経済苦の状況で、夫が実家に出ていくのが合理的だと思っていました。でも今思うと、ちょっと気の毒だったかな。殴られたり罵られたりしても苦でないという人は世の中にいませんから」
冷静に振り返られるようになったのは、離婚から時間が経ち、夫との関係について距離をおいて考えられるようになったからだ。
「夫は社会人になるまでアルバイトをした経験もなく、バブル期に就職したので就職の大変さも全く味わっていません。常に居心地のいいところにいないと気が済まない、ずっと陽の当たるところを歩いてきた人が、52歳になって足もとが揺らぐ体験に初めて見舞われてショックだったんだと思います」
そしてこう続けた。
「夫はまじめで、趣味や息抜きできることがないから、仕事が気に入らないとそこにだけ意識が向いてしまったのかもしれません」
なぜDVを止められなかったと思うか問うと、女性は「相談できる人や場がなかった」ことを一因に挙げた。
「私にも心を許して話せる友人が周囲にいなかった。両親に相談しても仕方がないという気持ちもありました。人をケアする職業に就いているのに、家に帰ってくると怒りのスイッチが入ってしまう。自分自身も精神が壊れていく、という自覚がありました。ですから、DVをしていた時から相談できる人や場所がほしかったんです」
女性はDV被害者の相談窓口にしかアクセスできず、そこでは精神科や心療内科の受診を勧められたという。
「医師はカウンセリングをするわけではなく、抗不安薬や睡眠薬を処方するだけ、というのは職業上、知っていましたから、その時点で諦めました。今からでもカウンセリングを受けられるなら受けてみたいです」
罪悪感を払拭したい、と吐露する女性に同情しつつ、疑問もぬぐえなかった。アンケートの回答欄に元夫を「クズのような人」と表現した人物とは乖離があるように感じられたからだ。その点を問うと、女性は「反省する気持ちと憎む気持ちが同居」する複雑な心情を明かした。
「自分が逆の立場だったら、あんな言われ方をされたら居たたまれないだろうなと客観的に考えられるようになって、反省の気持ちがわきました。でも一方で、クズみたいな人だったから私はDVをやってしまった、という気持ちもあります。その両方の心情が振り子のように行ったり来たりしているのが正直な思いです」(編集部・渡辺豪)
※AERA 2024年6月10日号より抜粋
AERA
2024/06/08 16:00