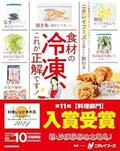「成り下がり」からの再スタート
「『湯木』の人間が、そない成り下がる必要が、どこにあるんや!」
難波の店で小料理店を始めることを告げると、父も母も眉をひそめて反対したという。
「成り下がり」――。
かつて船場吉兆があった「船場」は、大阪でも経済の中心地。「ええしの町」、つまり歴史ある大店が居並ぶ上流階級の町という印象がある。一方当時の「裏難波」は歓楽街で、夜の一人歩きをためらうような雰囲気が残っていた。
70まで「ええしの町」で商売を続けていた両親にとって、「湯木」の人間がそんないかがわしい町で小さな店を開くなど、「成り下がり」以外の何でもなかったのだろう。
しかし、背中を押してくれる人もいた。
「湯木さん、いつかあんたが自伝を書くとしたら、ここは『吉兆のボンボン』の再スタートにぴったりの場所ちゃうか」
そう言って励ましてくれたのは、事件直後から尚二さんを支え続けた、お好み焼き千房の会長中井正嗣さんだった。
尚二さんの復活を信じ、待ち続けていた人もいた。
「いつかまた使う日が来るのを待っていた。やっぱりこの器には、あんたの料理が一番映えるんや」
食器店の主人は、船場吉兆が破産した際、財産として没収され、オークションに出された器の一部を落札し、大事に保管してくれていた。
家賃9万円、6坪の店を開く
真っ白な割烹着を着ていた老舗料亭の三代目は、無職になり、人生の底に足がついた。ここからは服の汚れなど気にしてはいられない。壁に爪を立ててでも、よじ登っていくしかない。祖父である湯木貞一も、小さな料理店「御鯛茶処 吉兆」から、一代で「吉兆グループ」を確立していったのだから。
広さ6坪、家賃は9万円。カウンター席7席、テーブル席1つの「日本料理南地ゆきや」が、成り下がった「湯木尚二」の再スタートの地となった。
コンサル業で顔をつないだ相手に地道に営業を続けた甲斐もあり、店は初月で180万円の売り上げを達成。開店から1年経つ頃には船場吉兆時代の常連客でにぎわうようになり、店は手狭になっていった。
「個室があったら、商談にも使いやすいのになあ」
「夜はこの辺怖いから、友達を誘いづらいねん」
「この店、空調が利かな過ぎて暑いわ」
顧客の要望を受け、尚二さんは移転を決意する。移転先は「北新地」。大阪の銀座と呼ばれる高級飲食店街だ。2011年11月21日、北新地に「日本料理湯木」1店舗目を開店した。