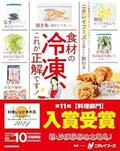「船場吉兆の次男坊」として
「吉兆の次男坊」「高級料亭のボンボン」……。このような湯木尚二さんに対する世間の印象は、あながち間違ってはいないだろう。「朝ごはんは吉兆の松花堂弁当だった」と語る彼の育った環境は、さすがに一般的とはいいがたい。
しかし、彼の幼少期はもう少し複雑だ。
尚二さんは、年の離れた兄とともに家政婦に育てられた。両親は料亭内の座敷で寝泊りしており、会えるのは週に一度。家族でどこかに遊びに行った記憶もなく、両親との距離は遠かった。
7歳のときに家政婦が病気で引退し、尚二さんは料亭に居を移すことになる。両親と共に暮らせる喜びよりも、母親代わりの家政婦と離れる悲しみが、幼心に深く刻まれた。
「一緒に暮らし始めたといっても、父も母もお客さん対応に飛び回っていますから、私にかまう暇なんてありません。学校から帰ると裏の空き地で壁を相手にキャッチボールしたり、四畳半の母の支度部屋で宿題をしたりしていました。寂しさはありません。子ども心に、『そういうものだ』とわかっていたんでしょう」
船場吉兆で働き始めたのは高校1年生のときだった。アルバイトとして、最初の1年間は玄関で客の迎え入れと見送り、次の1年間は皿洗い、3年生になったとき、ようやく厨房に入ることを許された。
「他の将来を夢見たことはありません」
祖父・湯木貞一氏は、料亭「吉兆」を5人の子どもにのれん分けした。以来、息子・娘はそれぞれ独立して「吉兆」を冠した料亭を営んでいる。貞一氏の三女である佐知子氏は「吉兆船場店」を譲受け、板前だった夫・正徳氏と共に経営していた。
貞一氏の孫は10人。当時、尚二さんより年上の男孫6人全員が、「吉兆の中の人」になっていた。決して後を継げと言われたわけではない。しかし、吉兆以外の将来を考える余地は残されていなかった。
「他の将来を夢見たことはありません。……ただ、大学4年生になると、友人たちが、みんなスーツで就活を始めるでしょう。それを見て、なんだか取り残されたような気持ちになりましたね」
生まれたときから将来が決まっている自分とは対照的に、無限の可能性を秘めた友人たち。その後姿を見送りながら、1992年、尚二さんは料亭「吉兆」に入社する。
26歳で店長を任される
当時の船場吉兆は拡大路線をとっていた。1995年、バブルが弾けてもまだ深刻な影響は出ていなかった時代。最初の支店は、ショッピングモール「心斎橋OPA」内に設けられ、尚二さんは26歳で父から店長に指名された。
1999年には福岡に支店を開店する。福岡は父・正徳氏の故郷。吉兆に婿入りし、大阪に根を下ろしてからも、いつかは故郷に錦をと願っていたのだ。
心斎橋OPA店を成功させた尚二さんは、並行して福岡店も任されることとなり、大阪と福岡を行き来する忙しい生活が始まった。
「福岡に出店すると決まったときは、正直不安でした。大阪と違って福岡は自分にとって未知の土地です。『湯木』の名前も通らず、顔も効かない場所ですから。しかし船場吉兆内で父の言葉は絶対。逆らうことなど考えられませんでした」
そしてここから、船場吉兆の黄金時代が幕を開ける。