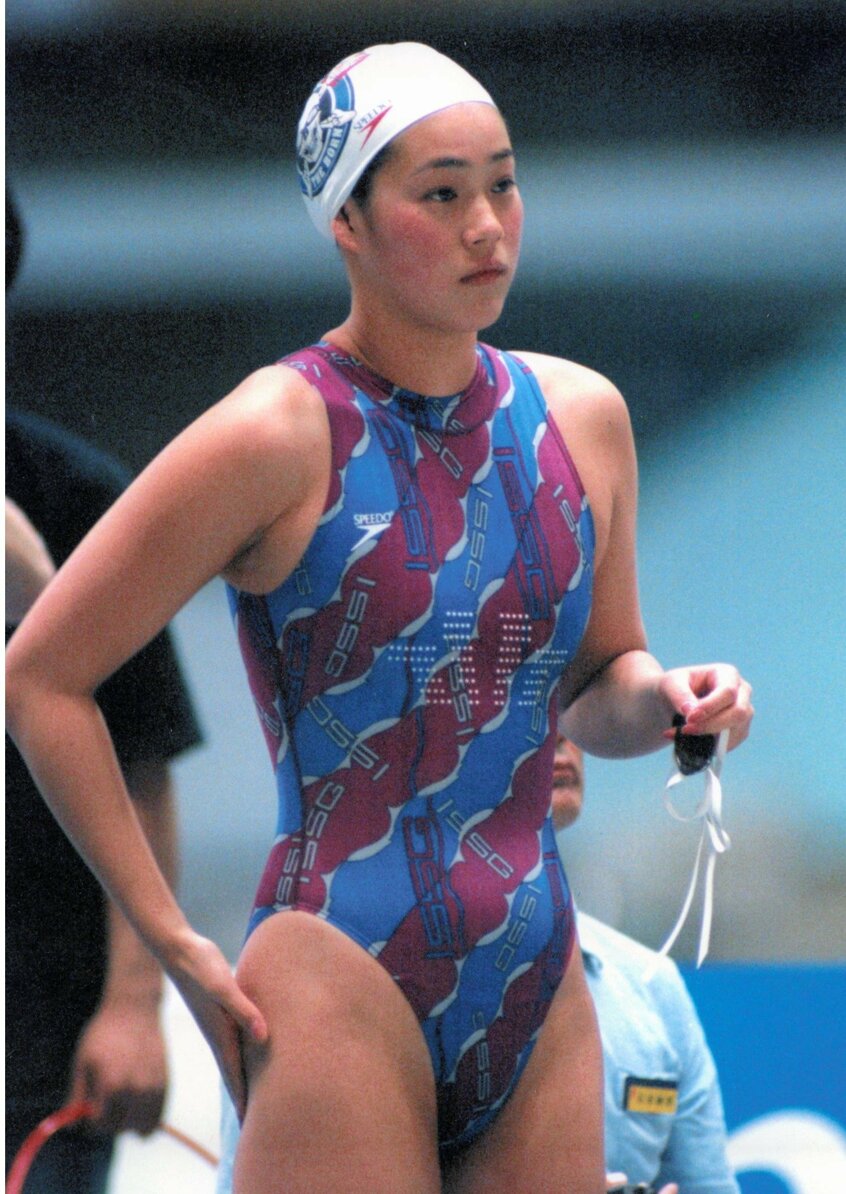
4年に1度の五輪に出場するためには、類稀な能力、才能だけでなく、日々の努力と鍛錬、そして運が必要になってくる。そしてようやく辿り着いた大舞台でも、自らの能力を存分に発揮し切れる選手はごく一部である。だが、その競技終了後の態度や発言、勝ち負けとは異なる場所と理由で、世間からの評価を左右したこともあった。
【写真】「ないっすー」で感動の銀メダル! 五輪でかつて注目を浴びたカーリング女子日本代表
この「負けて称賛」で最も有名なのが、1992年のバルセロナ五輪での男子マラソン・谷口浩美だろう。まだまだマラソンが日本のお家芸で、メダル獲得への期待が大きかった時代。前年の世界陸上で優勝した谷口は、金メダル候補の1人としてスタートするも、22.5キロ地点の給水所で後続の選手に左足のかかとを踏まれて転倒するアクシデントに見舞われた。靴も脱げ、30秒あまりのタイムロスを強いられた谷口は、最後まで力走したが、結果は期待値を下回る8位となった。そのレース直後のインタビューで、谷口は「こけちゃいました」と苦笑い。恨み節を一つも口にすることなく、笑顔かつ素朴な語り口調で「これも運ですね。精いっぱいやりました」と答えると、そのスポーツマンシップが大いに称えられ、同レースで銀メダルを獲得した森下広一よりも語り継がれることになっている。
同じく「負けて潔し」だったのが、2000年のシドニー五輪の男子柔道100kg超級に出場した篠原信一だ。前年の世界選手権で史上4人目の世界選手権2階級制覇を成し遂げた27歳は、五輪でも金メダルの大本命だった。その期待通り、順調に決勝まで勝ち上がった篠原は、決勝でダビド・ドゥイエ(フランス)と対戦する。そして1分半過ぎ、両者絡み合いながらも“内股すかし”を決めて相手の背中を畳の上に先に叩きつけることに成功した。しかし、これが「一本」とならず、逆にドゥイエの「有効」と判断され、そのポイントを覆すことができずに試合終了。その後、山下泰裕監督らが猛抗議したものの判定は覆らなかった。その後、「幻の一本」「世紀の誤審」と騒がれることになるが、試合直後の篠原は「自分が弱いから負けた」と一切、言い訳なし。その武士道を貫いた潔い姿があったからこそ、今も五輪の“名シーン”として語り継がれているのだろう。





































