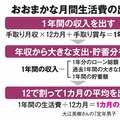面倒を見てきたのだから遺産の一部を分けてもらえると思っていたのに、男性と2人の弟の3人が「3等分から話し合おう」と切り出したためだ。男性は妻の苦労をわかっているつもりだったが、どうしてもギャップはある。
前出の佐山さんは、財産の一部を生前贈与しておくことが有効だという。
「新しい権利として認められたとはいえ、相続人同士は感情的になりやすい。介護される側がお世話になった人に、生前から配慮してあげるのが現実的です」
3番目は最低限の取り分(遺留分)をお金で請求できる制度。
相続人には最低限もらえる「遺留分」がある。基本的に法定相続分の2分の1だ。夫の遺産が評価額6千万円の自宅と預金2千万円の計8千万円で、相続人が妻と長男の2人のケースで考えてみよう。法定相続分は妻と長男がそれぞれ4千万円、遺留分はその半分の2千万円になる。
遺言では、妻に自宅の権利全てと預金1千万円、長男に預金1千万円を渡すと仮定する。一緒に暮らしてきた妻に自宅全てを譲るケースはよくある。この仮定だと長男は遺留分に1千万円足りない。これまでは長男が妻に不足分を請求すると、話し合いがまとまらない限り自宅が共有状態になってしまった。こうなると権利関係が複雑になり、自宅を処分しにくくなる。7月からは不足額をお金で請求できるようになり、共有状態を回避できる。
ここでのポイントは、不動産の資産が大きい場合、遺留分の請求に備えて手持ち資金を用意しておくこと。
「遺留分を頭に入れて残し方を考える。極端に偏った配分はもめる原因です。生前贈与や生命保険なども活用して、妻の手元にお金が残るようにしましょう」(曽根さん)
今回の改正では、残される配偶者に配慮した内容も目立つ。
結婚20年以上の夫婦なら、配偶者に贈与した家は相続財産の対象から外れる。気をつけたいのは、譲る意思をはっきりと示す必要があること。
来年4月からできる「配偶者居住権」についても学んでおこう。残された妻に自宅に住み続けてもらうために有効な制度だ。住宅の権利を「所有権」と「居住権」に分け、それぞれ相続できるようにする。配偶者が居住権を得ると、所有権が第三者に渡っても住み続けられる。
最終的に子どもに自宅を引き継ぐなら、子どもに最初から所有権を与えると、母が亡くなったときに「二次相続」が発生しない。納める相続税を抑えることにもつながるので、税理士らに相談しよう。
とはいえ、将来の引っ越しを考えているのなら、配偶者居住権は選ばないほうが無難だ。
「自宅は老後の資産として最後のとりで。配偶者居住権は売買できません。まとまったお金を手に入れる手段がなくなるので、所有権は持っておいたほうがよい」(佐山さん)
変更点はいろいろある。注意点も理解して、いまから備えておくべきだ。(本誌・池田正史)
※週刊朝日 2019年7月5日号より抜粋
こちらの記事もおすすめ 「自筆証書遺言」はこう書く! トラブル回避&失敗しないルール