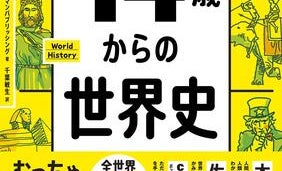20th Centuryが「週刊朝日」の表紙&カラーグラビアに登場!「V6があって今のトニセンが存在する」
今週の「週刊朝日」の表紙とカラーグラビアには「20th Century(トニセン)」が登場。1995年の結成から昨年11月の解散までV6として26年間を駆け抜けた、坂本昌行さん、長野博さん、井ノ原快彦さんの3人が、本格的に活動を再スタートさせています。井ノ原さん主演のドラマ「特捜9 season5」の主題歌「夢の島セレナーデ」も話題に。インタビューでは、3人が、“6人の変わらぬ絆”と“3人で目指すもの”を語りました。他にも、地域の力で問題に挑むシニアの「困りごと」解決マニュアル、話題の大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を13倍楽しむ方法、史上初めて誕生した現役東大生力士に高まる期待、運動能力調査などで高齢者の体力が軒並み上昇している話題など、盛りだくさんのラインナップでお届けいたします。
3人での活動が本格的にスタートしている「20th Century」。井ノ原快彦さん主演のドラマ「特捜9 season5」の主題歌「夢の島セレナーデ」にある「もがきながらも変わっていこう」というフレーズについて、長野博さんは「やっぱりもがかないと新しいことを生み出せない。でも、いやなことやってたら苦しいけど、そういうわけではない。楽しもうとする気持ちが大事なのかなと思います」。井ノ原さんはこのパートを坂本昌行さんに歌ってもらいたかったとのことで、「後輩や今の時代とどう向き合うかっていう、50代の人たちの思いを代弁しているという意味でも似合うと思って」。その坂本さんは周囲とのかかわり方について、「40代後半くらいから、僕のまわりにいる人が笑顔でいてほしいってずっと思ってて。いやな現場を見て、『なんかさみしいな。俺は違うやり方で進んでいこう』って思ったからかな」。経験を重ねたからこそ、3人それぞれの人生哲学がにじみでるインタビューとなりました。また、「特捜9」について井ノ原さんが語った記事も掲載。キャストやスタッフとのエピソードたっぷりでお届けしています。
その他の注目コンテンツは、
●「草燃える」の岩下志麻インタビュー 大河ドラマ「鎌倉殿の13人」を13倍楽しむ三谷幸喜脚本によるNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」が毎回、話題を呼んでいます。源頼朝の妻である北条政子役、小池栄子の演技が好評ですが、昭和のドラマファンにとって大河、北条政子といえば「『草燃える』の岩下志麻!」ではないでしょうか。岩下さんに北条政子、そして「鎌倉殿」について聞きました。「大河フリーク」の松村邦洋さんのインタビューや、鎌倉武士の武装や食生活など、読めば13倍面白くなる(?)お話をどうぞ。
●現役東大生の力士が誕生 やくみつる「相撲協会理事長を目指せ!」東京大学の現役学生である須山穂さんが角界に入り、大いに盛り上がる東大相撲部。東大相撲部の稽古の内容は? 歴史は? 学業との両立は? 東京都相撲連盟常任理事で東京大学相撲部OB会幹事長の白石浩三さんにお話を聞きました。また、漫画家のやくみつるさんは、大関ではなく「相撲協会理事長を目指せ!」と、今後への期待を語りました。
●週刊朝日と考える“幸齢者”ライフ! シニアの「困りごと」解決マニュアル運転免許を返納したため買い物に行けない、足腰が弱って重いものが持てない……。高齢になると、生活する上でさまざまな「困りごと」に直面するものです。楽しく快適に暮すために、地域の“資源”で解決できる方法が! 自治体の「緊急通報装置」レンタルや、シルバー人材センターに頼む見守りや付き添いなど、様々なテクニックを紹介します。また、高齢者の体力テストの結果が軒並み向上。“ムキムキ”シニアが増えているという特集もお見逃しなく。
●6月から業者に犬猫への装着を義務化 「ペットにマイクロチップ」どうする?6月1日に改正動物愛護管理法が施行され、販売業者などに対して、販売前の犬猫にマイクロチップを埋め込むことが義務化されます。飼い主になる際にも所有者の情報を登録しなければいけなくなります。果たしてその影響と、メリット、デメリットはどんなものがあるのでしょうか。ペットのマイクロチップ装着について考えます。
週刊朝日 2022年 5/27号発売日:2022年5月17日(火曜日)定価:440円(本体400+税10%)https://www.amazon.co.jp/dp/B09WQQGY65