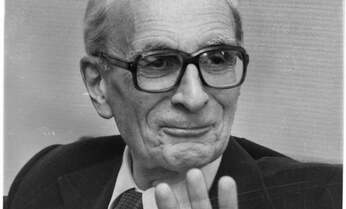8回予定の抗がん剤 6回目でリンパ腫が消えたのに続けるべき?【医師との会話の失敗例と成功例】
※写真はイメージです(写真/Getty Images)
病院に行き外来で主治医にいろいろ聞こうと思っていても、短い診療時間でうまく質問できなかったり、主治医の言葉がわからないまま終わってしまったりしたことはありませんか。短い診療時間だからこそ、患者にもコミュニケーション力が求められます。それが最終的に納得いく治療を受けることや、治療効果にも影響します。今回は、悪性リンパ腫で手術を行い、抗がん剤治療を受ける会社社長。8回予定の抗がん剤を6回目まで受けて、検査でリンパ腫が消えていることが判明。もうやめてもいいのでは?と考えます。医師との会話の失敗例、成功例を挙げ、具体的にどこが悪く、どこが良いのかを紹介します。
西南学院大学外国語学部の宮原哲教授と京都大学大学院健康情報学分野の中山健夫教授(医師)の共著『治療効果アップにつながる患者のコミュニケーション力』(朝日新聞出版)から、抜粋してお届けします。
* * *
「失敗例:エピソード1」と、「成功例:エピソード2」を順番に紹介します。
『治療効果アップにつながる患者のコミュニケーション力』(朝日新聞出版)
【患者の背景と現状】
Gさんは、66歳男性、会社社長です。日頃から健康管理には気をつけていて、毎年の職場健診に加えて、1泊の滞在型人間ドックも受けています。ある日、片方の睾丸が大きくなっていることに気づきましたが、痛みもないためしばらく放置。2カ月経っても元に戻らないため、かかりつけ医に相談したところ、「すぐに精密検査を」と言われ、紹介状を書いてもらって総合病院を受診。その結果悪性リンパ腫の診断を受け、睾丸の手術を行い、その後薬物治療を開始しました。
その抗がん剤治療は、入院し、最初の3日間の検査後、4日目と5日目に合計約8時間の点滴による投薬。その後は約20日間、感染防止のため入院生活を送るというものでした。退院後は10日ほど自宅で静養し、再び次の治療のため入院。それを8回繰り返すという計画でした。
男性は点滴終了後、脱毛、倦怠感、吐き気、食欲不振、便秘、それにしゃっくりが止まらないという副作用はあったものの、3、4回目までは「たいしたことはない。このくらいだったら8回でも9回でも」と感じ、医師や看護師にも「ほかの人もこの程度なの? みんなものすごく大変って言うけど、僕はそれほどでも」と豪語し、気分が良い日には院内を2時間程度歩くなど、「元気に」闘病生活を送っていました。
ところが、5回目、6回目となると、投薬後の回復に急に時間を要するようになりました。そして、6回目が終わった時点での検査でリンパ腫が消えていることが判明しました。
【エピソード1】
Gさん:先生、7回目と8回目の治療は必要ないのではないでしょうか。
医師:次の治療はあまり気が向かない、ということですね。リンパ腫は確かに消えたように見えますが、良くない細胞が残っている可能性があるので、予定通り8回行う必要があります。
Gさん:まあ、そうなのかもしれませんが。でも、会社のことも気になるし、そろそろ復帰しないと……。それにリンパ腫が消えているんだったら、もう治療は必要なさそうだし。副作用、結構大変ですよ、我慢してましたが。
治療中の体調や気持ちは変化するもの。患者は正直に、素直に体の状態や気持ちを医療者へ伝えることがよりよい治療に結びつく
イラスト/浜畠かのう 『治療効果アップにつながる患者のコミュニケーション力』(朝日新聞出版)より
医師:やっぱりそうでしたか。でも、1回目を始める前にいろんなことを考えて8回と決めていたわけですし、最後まで、というのは私たちの考え方なんですよ。
Gさん:でも、リンパ腫が消えてるのにあと2回、というのはどうも気合が入らないような、ですね、はい。
医師:そうですか。分かりました。これ以上、無理にと言うことではないですし、いいですよ、しなくても。
Gさん:本当ですか? よかった!
医師:ただ、一つだけお伝えしておきます。もし、再発したら、そのときは残りの7、8回目だけ、というわけにはいきませんよ。もう一度、最初からになります。
Gさん:そ、そうですか。分かりました。ちょっと家族や会社の者とも相談して、考えます。
【このときの医師の気持ち】
ここまでがんばったからこそ悪性リンパ腫がほぼなくなるところまで来られたのに。しかも、あんなに「たいしたことはない」と言って元気そうにしていたのだから、もう2回の治療を受けてほしかったところだ。でも、最後は患者さん自身が選ぶことなので、やりたくないものを無理にするわけにはいかない。再発した際、また最初からということははっきり言ったので、すべきことはした、というところだろう。
【解説】
抗がん剤治療は経験した人でなくては分からない体の辛さに加えて、特段何もしないで3~4週間入院し、退院してまたすぐに病院に戻るという、社会から切り離されたような疎外感にも耐えなければいけません。Gさんは口では「たいしたことはない」と言っていましたが、本音は決してそうではなく、毎回耐えられない苦しさと絶望感に悩まされていました。その分、検査の結果がんが消えていると知り、「もうこれ以上苦しい薬物治療を受けたくない、受ける必要もない」という気持ちだけが前面に押し出されて、医師とのやり取りがこのようになっています。何のために治療を始め、どうなればいいと考えるのか、また医師との信頼関係に悪い影響を与えかねない、という意味で「目的力」が不足したのがエピソード1です。うれしい気持ちが強かったのでしょうが、後先のことを考えずにそのときの気持ちを口にしたという点で、「発信力」にも問題があったと言えます。
【エピソード2】
Gさん:がんが消えてると聞きました。よかった! これまでの治療が効いた、ということですね。
医師:確かにそうです。これで6回目が終わったので、あともう一息。7回目と8回目、がんばりましょう。
Gさん:え? 治ったんだったら、もう薬物治療は必要ないのではないんですか?
医師:そう考えられないこともありません。あくまでもGさん次第ではありますが、一つ大切なことを申し上げると、もし、もしですよ、再発したら、そのときは残りの2回だけ、というわけにはいかないんですよ。最初からやり直しで、場合によっては8回でも終わらないかもしれません。
Gさん:そうなんですか。でも、これまで半年以上会社はほったらかしで、そろそろ戻らないと……
医師:それはよく分かります。しかし、Gさんはついこの前まで「副作用は思っていたほどたいしたことはない」って言われていて、私たちもGさんを見て、「思ったより元気にされているな」っていつも話してたんですよ。
Gさん:まあ、少しでも体力をつけて、いつでも仕事に戻れるようにと、少し無理もしていました。そして、「副作用はたいしたことはない」って言ってたのも自分を元気づけるためで、本当はかなり辛かったんです。お恥ずかしい話ですが、この5回目と6回目のときは「もう、いや。早く家に帰りたい」と泣きたくなるような気持ちでした。
医師:そうだったんですね。よく我慢してがんばってこられました。だからこそあと2回、目には見えないがん細胞をたたいて、徹底的に治療をしておいたほうがよいと、私たちGさんの治療を担当した全員が思っています。今は薬も良くなっていて、10年前だったらこの治療は無理だったくらいですよ。
Gさん:(しばらく黙って考えて)分かりました、先生。プロの判断を信じてあと2回、がんばります。
【この時の医師の気持ち】
予想していたよりずっとGさんが元気そうにしていたけど、実はやはり辛かったんだ。確かにこれまでの同じ薬物治療を受けてきた患者さんよりはとても体力もあって元気そうに見えたけど、かなり我慢していたことがGさんの口から直接聞くことができてよかった。7、8回目の治療を今回はしない、という選択肢もあるけど、これだけ一生懸命苦しい治療に正面から向き合ってがんばってきたGさんの今後のことを考えると、ここはもう一歩踏ん張って治療を受けることを納得してくれて、そしてわれわれを信頼してくれていることも確認できた。これからも親身に、そして全力でGさんの治療に当たっていこう。
【解説】
Gさんはエピソード1と比べると、1回の発言で一つのことだけに絞って医師に自分の気持ちを伝えている、という違いがあります。「何のためにこのメッセージを発しているのか」という目的力が強く働いたため、医師とのコミュニケーションの焦点が明確で、一つひとつの用件を順番に果たしている、という違いがあります。そうすると、医師も論点を絞って一段ずつ階段を上るように、そして患者とともに上るように努力することができます。短い発言の中にあれもこれもと、多くの内容を込めると、どんな場合でも問題を直視して解決することが難しくなります。
また、Gさんは自分の感情を正確に認識し、これまで態度には出さなかったかもしれないが、実は肉体的にも精神的にも辛く、やっとの思いでここまで来たことを正直に、素直に示していることにも説得力を見いだことができます。エピソード2の最後は「おまかせ」というメッセージを発していますが、何も考えずに「お医者様に丸投げ」ではなく、自分で考えた末、医療者たちを信頼したうえで任せる、という強い意思を確認することができます。
※『治療効果アップにつながる患者のコミュニケーション力』(朝日新聞出版)より
宮原 哲/西南学院大学外国語学部教授
1983年ペンシルベニア州立大学コミュニケーション学研究科、博士課程修了(Ph.D.)。ペンシルベニア州立ウェスト・チェスター大学コミュニケーション学科講師を経て現職。1996年フルブライト研究員。専門は対人コミュニケーション。ヘルスコミュニケーション学関連学会機構副理事長。
主な著書:「入門コミュニケーション論」、「コミュニケーション最前線」(松柏社)、「ニッポン人の忘れもの ハワイで学んだ人間関係」、「コミュニケーション哲学」(西日本新聞社)、「よくわかるヘルスコミュニケーション」(共著)(ミネルヴァ書房)など。
中山健夫/京都大学大学院医学研究科健康情報学分野教授・医師
1987年東京医科歯科大学卒、臨床研修後、同大難治疾患研究所、米国UCLAフェロー、国立がんセンター研究所室長、京都大学大学院医学研究科助教授を経て現職。専門は公衆衛生学・疫学。ヘルスコミュニケーション学関連学会機構副理事長。社会医学系専門医・指導医、2021年日本疫学会功労賞。
主な著書:「健康・医療の情報を読み解く:健康情報学への招待」(丸善出版)、「京大医学部で教える合理的思考」(日本経済新聞出版)、「これから始める!医師×患者コミュニケーション:シェアードディシジョンメイキング」(医事新報社)、「健康情報は8割疑え!」「京大医学部のヘルスリテラシー教室」(法研)など。