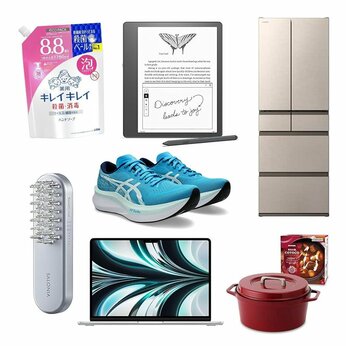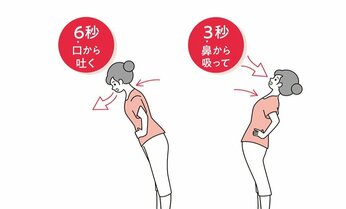留学する若者の夢を踏みにじる斡旋業者はなぜ無くならない? 法規制進まず留学システムに穴
写真はイメージです(写真:Getty Images)
カナダ留学の事前説明で素晴らしいプログラムであることを謳い、現地で実態とかけ離れた留学であることが多数報告されているという。AERA 2024年10月14日号の記事より。
* * *
カナダでは、新たにできた留学制度の被害報告が上がり始めている。語学の学びに加え現地企業で有給のインターンシップ(就業体験)をしながら学べるとうたう「Co-op(コープ)留学」という制度。マーケティングなどを企業内で実践的に学べると各斡旋業者が広告を出して募集している。農家やカフェ店員などが多いワーキングホリデーと比べると、オフィスワーカーとして働けるのが魅力の制度なのだが、実際にインターンシップまでこぎ着ける人は少ない。
実力と合っているか
カナダ留学に詳しい「カナダクラブ」の大澤眞知子さんの所にも、最近Co-op留学がらみの相談が寄せられているという。日本の大学を休学して1年間のCo-op留学に申し込んだ学生からの相談メールには、渡航してみると期待していたサポートはなく、解約したいができないと書かれていた。学生は、留学エージェントに相談の段階で英語に自信がないことを話していた。だがエージェント側は「語学学校で半年勉強するから大丈夫!」と、Co-op留学を勧めてきた。現地に行くと授業は講義スタイルのただの語学研修で、追加料金を払って留学生のための英語の授業も受けたが、マーケティングのインターンシップに応募できるほどの力もつかず、インターンシップ先を探すためのサポートもなかった。大澤さんによれば、カナダの企業でインターンシップをするには、TOEFLだと100ぐらいのスコアが必要だという。「現地の大学や州立のカレッジに入り、英語で専門知識を学び、マーケティングなどのスキルを身につけてからインターンシップに行くなら分かります。英語力もそれほどないのに、大丈夫だと押し切るような業者は気をつけないといけない」(大澤さん)。留学は支払う金額も高いため、やめて新たに留学するのは経済的に難しい人も多い。大澤さんは「申し込むプログラムと本人の実力が合っているかを必ず考えてほしい」と忠告する。
AERA 2024年10月14日号より
留学を巡るトラブルは今に始まったことではない。08年には留学斡旋業者「ゲートウェイ21」の破綻による大規模な被害が世間を騒がせた。国民生活センターに寄せられる相談件数は、コロナ禍の影響があった年を省いても、毎年年間300件を超えている。大人の留学も含めた件数とはいえ、それでも多い。このほかにも弁護士などへ直接相談する人や、泣き寝入りで終わる人もいるため、トラブルの件数はさらに多いとみられる。一方で、政府の教育未来創造会議(議長・内閣総理大臣)は咋年4月、留学する高校生の人数を2033年までに12万人にすると目標を示している。
法規制なされないまま
「なんの規制もないのが問題なんです」と話すのは、兵庫県弁護士会の鈴木尉久弁護士だ。例えば、旅行業を開業する場合は営業保証金や弁済業務保証金など、万が一の場合に消費者を救うためのお金を用意することが義務づけられている。ところが、留学斡旋業の開業にはこうした規制がまったくない。兵庫県弁護士会は過去に2回、留学斡旋業者に対し法的規制を設ける意見書を関係諸官庁に送付したこともあるが、法規制はなされないままだ。
鈴木弁護士は「保証金制度で消費者が全部守られるわけではないですが、保証金を用意できない人は事業所が開けないため、参入障壁にはなります。優良な事業者だけが残る二次的効果はあるはず」と、規制の必要性を訴える。その上で、消費者側の注意も必要だと話す。
「留学斡旋業は仲介業です。不動産売買で考えてみてください。不動産会社に仲介手数料は払っても、物件のお金は売り主と買い主で直接やりとりします。留学斡旋の場合も本来は学校とのお金のやりとりは、留学者と学校で直接やるべき。仲介業である斡旋業者に全部預けるのはトラブルのもとです」(鈴木弁護士)
通信機器の発達で海外とのやりとりのハードルも下がった。法整備が進まない中、留学を目指すなら、大事な契約は自分で握っておくことが賢明だ。
(フリーランス記者・宮本さおり)
※AERA 2024年10月14日号より抜粋