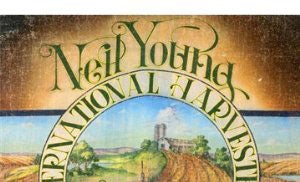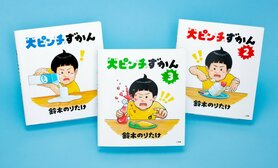第35回 NEIL YOUNG / HARVEST MOON
パール・ジャムのデビュー作『TEN』。《スメルズ・ライク・ティーン・スピリット》を含むニルヴァーナのセカンド・アルバム『ネヴァーマインド』。バブル的なトレンドに音楽界全体が翻弄された80年代は去り、新たなロックの時代が幕を開けたのだということを明確に伝えてくれた2枚の傑作は、91年の夏から秋にかけて相次いでリリースされている。ニール・ヤングの「復活」と時期が重なるわけだが、シアトル地区から登場した2つのバンドは、彼からの影響を認めていた。パール・ジャムはこのあと何度もニールと共演しているし、94年の春に自殺したニルヴァーナのカート・コベインは、よく知られているとおり、その遺書に彼の歌から抜粋したものと思われる言葉を残している。 そういった状況から、グランジのグランドファーザー、ゴッドファーザーなどと呼ばれるようになったニールは、しかし、『ラグド・グローリー』ツアーとライヴ盤『WELD』の制作を終えると、180度方向を変え、ナッシュヴィル系のミュージシャンたちとアコースティック・サウンドに徹したアルバムをつくり上げている。92年秋発表の『ハーヴェスト・ムーン』だ。 そのタイトルは、ちょうど20年前に発表され、ニール・ヤングというアーティストを頂点へと押し上げるとともに、苦悩も与えることとなった『ハーヴェスト』とダイレクトに重なるもの。ベン・キース、ケニー・バットリィ、ティム・ドラモンド、ジェイムス・テイラー、リンダ・ロンシュタットなど、参加アーティストの顔ぶれはほぼ重なっていて、ジャック・ニッチェもストリングス・アレンジで協力している。ただし、『ハーヴェスト』のハイライトでもあった「ワーズ」や「アラバマ」のように力強くエレクトリック・ギターを弾きまくる曲は、ここにはない。じつは、ニールは『WELD』の制作などで耳を痛めていたらしく、「轟音はしばらく」という気分にもなっていたようだ。 20年前のアルバムとのつながりは彼自身も強く意識していたはずだが、背景にあるものとしてそれ以上に大きかったのは、障害を持って生まれた息子との共生がいろいろな意味で軌道に乗ったことと、その過程でより深いものとなっていった妻ペギへの愛だと思う。