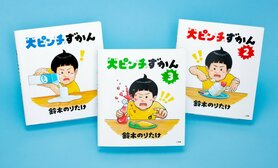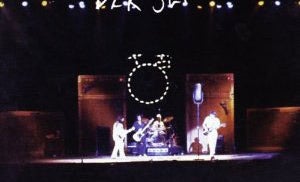
第25回 RUST NEVER SLEEPS / NEIL YOUNG & CRAZY HORSE
1970年代の半ば、ロックをめぐる状況は大きく変わろうとしていた。そのもっとも顕著な現象が、過度な商業化。60年代後半の激動の時代、ロックはカウンター・カルチャーを象徴する音楽であったはずなのに、いつのまにか、数百万枚もアルバムを売り上げるアーティストが珍しくなくなっていた。もちろん売れること自体は悪でも罪でもなんでもないが、自然な流れとして、売上が評価の尺度として定着してしまったのだ。大きな変化のもうひとつは、明らかにその反動といえる、パンクの台頭。自らも、「ハート・オブ・ゴールド」が図らずも全米1位を記録したことからさまざまな苦悩を味わい、徹底して自分らしく表現することにこだわってきたニール・ヤングは、そういった時代の変化を独自の視点で受け止めた。その最初の成果が、「消え去るよりは燃えつきたほうが」、「サビは眠らない」というフレーズをロック史に残すこととなる名盤『ラスト・ネヴァー・スリープス』だ。