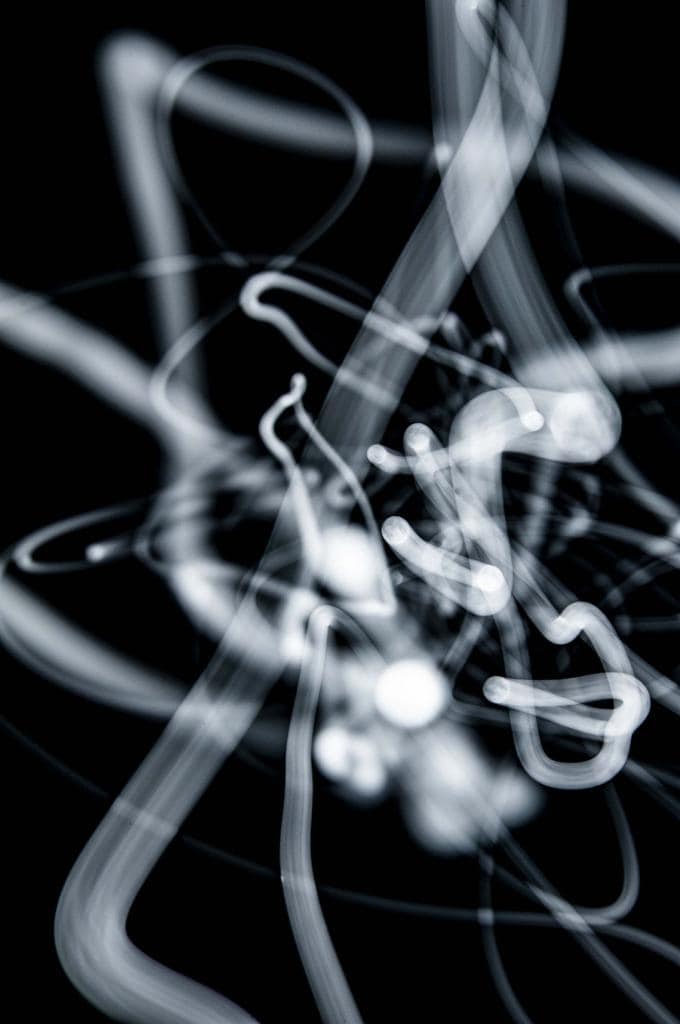
しかし、さらなる病が襲った。
「その2、3年後、脳梗塞をやってしまったんです。半身まひ、言語障害になってしまった。小説も書けなくなってしまった」
深沢さんはしばらく、そのことを知らなかったという。
「『深沢には言うな』、みたいなことを家族に言っていたみたいです。でも、1年くらいして彼の妻から『実はいま、こんな状況です』って、メールがあった。その後、本人とも電話でしゃべった。『治ったら遊び行くわ』みたいな、結構明るい感じだった。でも、姿はあまり見られたくないだろうから、そのままにしておいたんです」
鶴岡さんが亡くなったのは19年の初夏だった。
<彼の妻から久方ぶりに報を受け、翌朝車で彼の住む信州の山の中に向かう。昼過ぎに到着した。時間は巻き戻せない>(『よだか』ふげん社)

■「じゃあ、わかりました、とは行けなかった」
鶴岡さんが亡くなった翌年、深沢さんは上田で写した写真と鶴岡さんの文章を組み合わせ、作品にまとめた。
「それは悲しみしか写っていないものだった。彼の顔写真が結構入っていた。死を思わせるような写真もあった。彼は俳句を何百首も残して死んだんですけれど、死にちかい句をぼんぼん載せた」
それをふげん社に持ち込むと、「ちょっと重いよね。見てよかったって思えるものがいい、という話になったんです。それで、『もう一つ、世界をつくってみたら』って、言われた。なるほどな、と思った」。
しかし、深沢さんは気持ちを吐き出さずにはいられなかった。
「もう一回、構築してみたらいかがですか、とは言ってくれたけれど、じゃあ、わかりました、とは行けなかった。自分の気持ちに落とし前をつけたかった」
そして開いたのが、冒頭に書いた写真展「山の阿房(あほう)」だった。
「写真展の案内は1枚も送らなかった。自分と鶴岡のためだけの、ごく私的な展示だったんです。それで区切りをつけた」
深沢さんは沈黙し、口を開くと、こう続けた。
「彼とは18から20歳くらいまで濃密な時間を過ごしたんです。新宿界隈で8ミリ映画をつくったりした。彼が亡くなって、ああ、彼とぼくはお互いに分身だったな、と思った。なんか、目はかすむし、見るものがぼやけるような感じだった。ピントもぜんぜん、合わなくなってしまった。それがだんだんまともになってきた。星とかを撮っているときに直していったんでしょうね。2年くらいかかったかなあ」と、振り返る。
 米倉昭仁
米倉昭仁



















