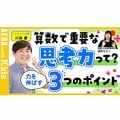「緊張感が高まりすぎて、あたふたしてしまうのはよくない。けれど、気持ちが緩み、集中力が切れてしまうのはもっと怖い。適度な緊張感を保ちながら、自身の行動を振り返ることができるアドバイスを一つ示してあげると、気持ちが安定するんです」
逆に親が注意すべきは、「~はちゃんとやったの?」と焦りをそのまま言葉にのせ、ぶつけてしまうことだ。
「子どもはすべてに手をつけようとし、結果、中途半端になってしまう。そう言い続けられた子どもは危ないんです」
いまの子どもたちのなかには、繊細な子も多いとも感じている。「負荷をかけすぎない」ことも大切だという。
■プリントを積み上げる
算数のプロ家庭教師で中学受験専門カウンセラーでもある安浪京子さんは言う。
「私自身、前日や前々日といった超直前期に子どもたちに伝えているのは、『全然眠れなくても合格した子もいるので大丈夫』といった、すべてにおいて安心できる声かけです」
「頑張れ」という言葉が効く子もいれば、プレッシャーになる子もいるという。
「『どんな結果でも受け入れるから、思いっきりやっておいで』という言葉が刺さる子が多いとは思いますが、そうした言葉に対し、『私は合格するためにやってきたんだぞ』と反発する子もいる。その子にどんな言葉が効くかということは、親御さんがじっくり観察してください」
安浪さんが何よりも響くと感じているのは、「これだけやってきた」という事実を親子で振り返ることだ。4年生から使用してきた教科書やプリントを積み上げてみる。すると、小学生の身長を優に超えるくらいの高さになることもある。
「量を見せて、『こんなにやってきたのだから、自信を持って受けてほしい』と声をかける。それが、親にできる最大のはなむけの言葉なのではないかと思います」
中学受験は、体力的にも精神的にもハードな長期戦だ。東京で暮らす子どもの場合、2月に実施される本命校の試験を受ける前に、埼玉、千葉といった入試解禁日の早い近郊エリアの中学校を前受けすることが一般的だからだ。1月の前受け校での合格は“お守り”になるうえ、本番の空気に触れられるなどのメリットがあるため、多くの受験生が複数の学校に挑むのが一般的だ。だがその分、合格が続くと、目移りし、第1志望へのこだわりが一時的に薄れてしまうこともある。前受け校に合格し、気持ちが浮つき、躁状態になっている子どもも少なくない。