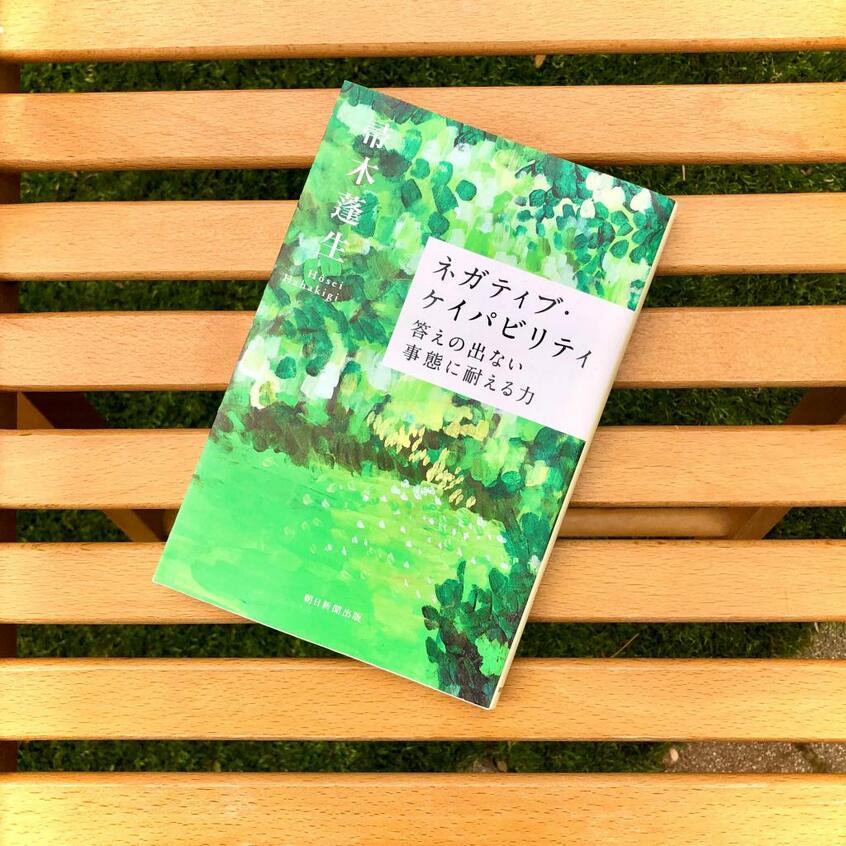
――今の日本で、ネガティブ・ケイパビリティは、どんな人たちに響いているのでしょう。
この前は、ビジネススクールからインタビューに来ましたよ。イケイケドンドンばかりじゃいけない、壁にぶち当たったらどうするか、ネガティブ・ケイパビリティが必要だ、ということだそうで。これまたびっくりしました。
――簡単に「解決」しないことがある、ということですね。
ネガティブ・ケイパビリティの話をするようになったのは、20年くらい前からでしょうか。最初は精神科医の内輪の会で話して、「へえ、そんな概念があるんですか」と驚かれました。だから反響も、まずは医師の世界での話だったのです。薬物依存に詳しい精神科医から「依存症治療にネガティブ・ケイパビリティは不可欠ですね」と言われたことがあります。私は、ギャンブル依存の患者さんを診ていますから、「それはそうでしょう」と答えました。それから、透析患者さんを診ている医師たちからも呼ばれて話をしました。透析患者さんとは、ずっと付き合っていかないとなりません。そして、腫瘍や、終末期医療、介護、リハビリに関わる人たちからも、手紙をいただいたり、声をかけられたりしました。
――抱えて生きていかなければならないことも、ありますよね。
『ネガティブ・ケイパビリティ』の本を出したら、看護雑誌からもインタビューが来て、『看護教育』という雑誌の「問題解決志向に疲れたら……」という特集で紹介されました。看護も解決志向のところがあって、情報をアセスメントして、さあこの方針でいきましょうと計画を立ててやってきたわけですけれど。解決志向だけでは、疾患を抱えて生きる患者さんたちをケアすることはできないのではないか、という深い問いかけがあったようです。
また、教育の分野で受けとめられて、目から鱗でした。関西大学のウェブサイト「執行部リレーコラム」にこの本のことを書いてくださった方がいて。わからないことを探って熟考するのが教養であり、学生たちのネガティブ・ケイパビリティを我々はどうやって涵養すべきか、というようなことが書いてありました。
入試問題に採用されたのも、うれしかったですね。


































