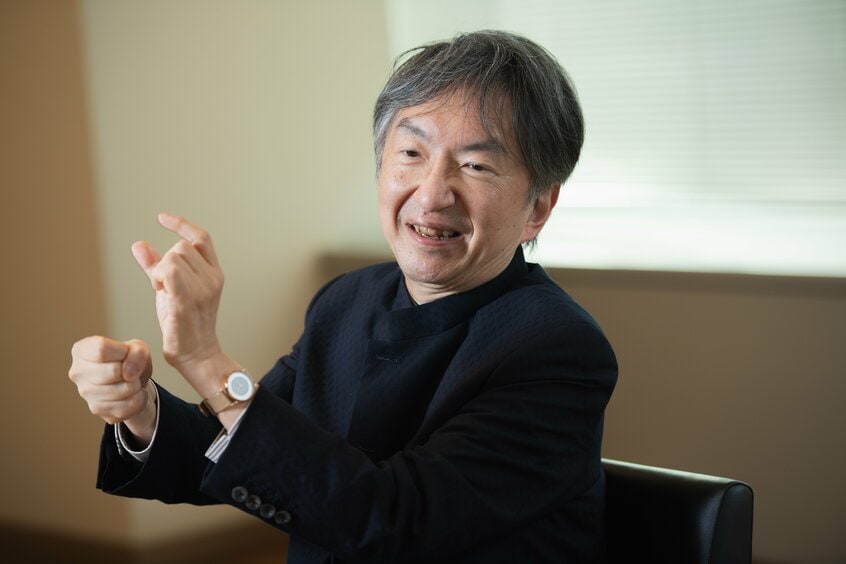
片山 徳川将軍が15代続いたのが江戸時代です。征夷大将軍は武家の棟梁に与えられる朝廷の官職ですが、徳川家にその他の武家が従うのは、武士という特権階級のリーダーだからであって、その意味では、確かに天皇は必要ありませんよね。
江戸時代は人口の3%くらいしかいない特権階級の武士をその他の人々が食わせるというかたちで、天下泰平がずうっと続いていました。これは鎖国の恩恵と言えます。外圧があったら、日本のような海岸線の長い国を守るためには、武士だけではまったく足りず、昔の防人(さきもり)のように国民総動員で行かないと無理なわけですから。
そこがあらわになるのが幕末ですね。急激にロシアやアメリカから外圧がかかってきた時に、武士だけではどうしようもない。それで戦闘員を増やすには、古代の中央集権の「一君万民」というモデルに戻るしかないとなる。王政復古ですね。でも近代科学や近代産業やお金も必要だから、結局、明治維新は王政復古モデルと近代化モデルの合わせ技になるわけです。
攘夷のほうは、たとえば攘夷思想の親玉というべき水戸学の会沢正志斎(あいざわ・せいしさい)でも、最後には攘夷は今すぐ無理だから時を待って、ということを言いだす。つまり、西洋文明を取り入れて国力がついてから攘夷するしかないというのが、攘夷思想家の落ち着きどころだったわけです。四民平等で国民を作り、工業生産力を上げて、教育で労働力も上げて、軍隊を強くしていく。その先にまた攘夷をやれるかもしれない。でもそれは傍流の思想ですね。主流はそのまま西洋近代の一員になってめでたしめでたしというほうで。頭山満(とうやま・みつる)などのいわゆるアジア主義の反西洋近代的なモチーフはやはり日本近代の脇役です。
それが第一次世界大戦後に世界大恐慌があって、国際協調主義かそれを捨てるかという究極の選択を迫られる危機の時代になって、攘夷のモチーフがアジア主義などとも結びついて再帰してくる。会沢正志斎の予言通りになってくるのですね。もちろん尊皇を伴って。(後編に続きます)
(構成/高橋和彦)








































