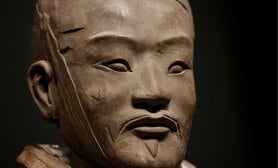思考停止社会から抜け出すために
「さっきも言いましたけど、僕は『自分の頭で考えること』を本当に大事だと思っています。でも、自分で考えること、悩んで自問自答することって、自分に刃を向けることと同義だと思うし、しんどいというのもわかっている。だけど、やっぱりそれを拒んではいけないと思ってしまうんです」
自分の頭で思考することと、世の中がどんどん息苦しくなっていること、そして本が読まれなくなっていることは相関関係にある気がする、とも話す。
「本を読むことで、自分ではない誰かの思考や人生を追体験する。それは負荷のかかる作業なのかもしれないけれど、みんながその苦しい作業を拒否して、ラクをしようとしすぎた結果が今のこの状態なんだとしたら、この『今』が正解なはずはないと思うので」
自分の考えとは違う意見に出会い、受け入れるのは、確かに努力を要する。自分が正しいと信じて疑わない人ほど、SNSなどの仮想空間で相手を裁こうとする。
「ものごとを単純化しすぎて、すべてを白か黒かで仕分けてしまう。『あわい』がなくなってますよね。この物語の主人公の十和だって、やる気なく惰性で塾に通っていたころは、大人というものをひとくくりにして見くびっていたと思うんです。受験までの一年を通じて、彼女が得たもっとも大きな気づきは『捨てたもんじゃないと思える大人もいる』ということなんじゃないのかな」
「ヒステリックに子どもを勉強に向かわせようとする親が、カッコイイわけがない。かっこよく生きている姿を見せることのほうが、いいとされる学校に導くよりずっと大事。どうせ伝わらないと諦めそうになりますけど、子育ても、執筆も歯を食いしばってがんばります」
愛する娘のために、世知辛い東京に暮らす父・早見和真は、「彼女が高校を卒業するまであと3年。東京暮らしに耐え忍んで見せますよ」と笑う。
いい学校には入ってほしい。しかしそれが本当にわが子の幸せなのか? 親も子も、迷い、考え、衝突し、模索する。そんな「普遍なテーマ」を、早見和真の著書『問題。』は私たちに問いかけてくる。
こちらの記事もおすすめ 大阪の「高校無償化」影響し、関西の中学受験率が過去最高 志願者数が増えた付属校とは?【中学受験2025】