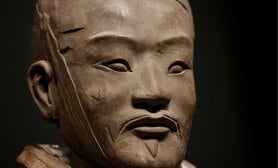たった12年の人生経験から、進む道を自ら選ぶ難しさ
「僕は自分のワガママで娘を翻弄しているという負い目がずっとあったんです。彼女は僕が作家デビューした一年後に都内で生まれたんですが、当時はどうしても執筆のために東京を離れたくて、伊豆半島の河津町というところに引っ越しました。そこで彼女は楽しく育っていたんですけど、幼稚園を出るタイミングでまた僕が勝手なことを言い出して、さらに縁もゆかりもない愛媛県松山市に移住します」
ついていく家族も大変だったと思うが、そんな娘に、この父はさらなる難題を言い渡していた。
「『申し訳ないけど、12歳まではこうしてあなたの人生を翻弄することになる』って、彼女が物心ついた頃からずっと言い続けていました。『その代わり、中学校は世界中の学校から好きなところを選んでいい』と」
とはいえ、小学生の少女に世界を簡単に想像できるはずもないこともわかっていた。
「おそらく妻と娘とで話し合ったんだと思うんですけど、小6の夏休み前に『東京の学校に行きたい』と言い出したんですよね。えー、つまらなくない? と真っ先に思ってしまったんですけど、約束は約束だったので。受け入れることに決めました」
お嬢さんは見事志望校に合格し、家族は今東京に住んでいる。
「受験にまつわるいろいろなルールが信じられませんでした。たとえばたくさんの学校を見学して、志望校を決めるということすら僕はピンとこなかった。子どもはその学校の何を見るのだろうって、自分の子ども時代に照らし合わせてみたら本当に理解できなくて。親が『いい学校だね』と言えば、子どももなんとなく『いい学校なんだ』と思うようになる気はします。でも、僕はその誘導を正しいこととは思えなくて。その刷り込みにどういう意味があるんだろうって」
「これが仮に『親の希望する学校に入ったら必ず幸せになれる』という保証があるなら、僕もいろいろと誘導したと思うんです。だけど、第一志望に落ちたおかげで幸せになる可能性だって同じだけあると思ってしまう。たとえ世間的に評価の低い学校だったとしても、そこで生涯の友達や恩師に出会えるかもしれないわけで。そこはもう運でしかないのではないかと」
「結局、突き詰めると、僕は娘に幸せな人生を送ってほしいだけなんですよね。そのために必要なのは、べつにいい学校に入ることじゃなくて、たとえば自分の頭で考えられることだったり、自分自身で人生を切り拓いていける力なんだと思うんです。どうしたらそこに近づくことができるのか。もちろん「一生懸命がんばること」という前提は必要とすると思うのですが、それだって疑わなきゃいけないのかもしれない。『がんばらずに生きていけるなら、そっちの方が幸せじゃん』という弁に立ち向かえる言葉を僕は持っていない。いずれにしても、受験の合格・不合格より大事なことはたくさんある気がしちゃうんです。それが何なのか、親としても自分の頭で考えなくちゃいけないんじゃないかって」