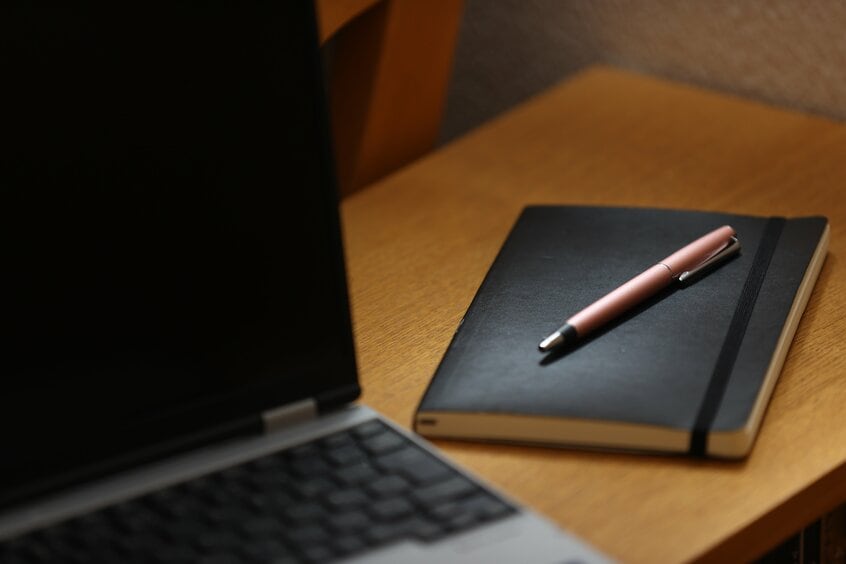
現在、生殖医療でごく日常的に用いられている“凍結保存”は将来に妊娠・出産の可能性を残せる技術だ。選択肢が広がる一方で、新たな葛藤も生まれている。AERA 2025年3月10日号より。
* * *
「年齢を考えると、できることなら、今すぐにでも妊娠して子どもを産みたい。でも相手がいなくて、それが叶(かな)わない。そんな中で将来に産める可能性を少しでも残しておきたくて、卵子凍結したんです」
外資系コンサルティング企業に勤める41歳の女性は、こう口を開いた。女性が卵子凍結したのは、40歳を迎える誕生日を翌月に控えたタイミング。パートナー不在の中、「40代という数字に焦ったところもあった」と打ち明ける。
仕事中心の生活を過ごしてきた20~30代。社会に出て忙しい日々の中、「子どものことなんか考える余裕がなかった」とこぼす。交友関係も広く、都心で過ごす一人の生活は、忙しくも充実していた。
ある程度キャリアを築き、「そろそろ家族がいたらいいな」と思い始めた30代半ばに突き当たったのが、新たな相手と出会うことのハードルの高さだった。特に結婚相談所などの婚活の場では、「女性の価値は、これほどまでも年齢で判断されるのか」と打ちのめされたという。妊娠・出産のタイムリミットを意識せざるを得ない中、焦燥感の中で出会いを求める日々に、いつ終わりが訪れるのか、見当もつかない。卵子凍結は、そんな中で、自分一人でも将来の妊娠・出産に向けて備えられる“唯一の手段”でもあった。
適齢期は20~30代前半
3回の採卵手術で合計18個の卵子を採取し、現在もクリニックで凍結保管し続けている。1回の採卵ごとに約40万円かかり、保管費用などを含めて、卵子凍結のために支払った金額は120万円を超えた。
「確かに大金ですが、将来のために、今自分でやれることはやったという達成感はあります」(女性)
卵巣から卵子を体外に取り出し、将来の妊娠に備えて凍結保存する卵子凍結。もともとはがんや白血病など病気の治療で生殖機能を失う可能性のある女性たちを対象に行われていた医療行為だったが、女性の社会進出とともに晩婚化、晩産化が進む中で、健康な女性が将来の妊娠に備えて行う「社会的適応」と呼ばれる卵子凍結が少しずつ広がってきた。東京都が2023年度から卵子凍結の費用助成を始めたのを皮切りに認知度が大きく広がり、昨年からは山梨県も助成をスタートするなど、行政による支援の動きも広がっている。






































