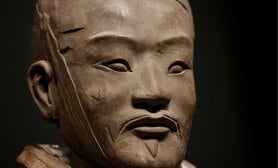結局、題字だけで200枚ずつ4回書いて提出した。番組のホームページでもインタビューを受け、全国から講演に招かれるなどするうちに根本の名は高まっていった。伝統ある日本橋三越本店での個展を若い彼が実現できたのも「光る君へ」効果である。
「これまで自己紹介に30分はかかりましたからね。『書道家って大きい字を書くんじゃないの?』『「夢」や「努力」って書かないの?』なんて言われて。それだけ仮名書道は知られていないんです」
アルバイトの掛け持ちで学費や謝礼金を捻出
根本は1984年、埼玉県に生まれた。父は彼が1歳の時に亡くなり、その後は祖母と母に育てられた。根本はおばあちゃん子を自認している。
「スナックを経営している母は忙しかったので、僕はおばあちゃんが母親だったようなものです。書の道に入ったのも、小学校2年生の時、おばあちゃんが『男の子は字がうまくないと説得力がない』と言って、年金をやりくりして町の習字教室に通わせてくれたから」

その時は堅苦しいルールが多いと感じて小6でやめてしまったが、中学2年で仮名書道に出会う。母のお店に来ていた常連が仮名書道家で、根本は彼が見せてくれた、色鮮やかな紙に散らし書きされた「古今和歌集」の写本に一瞬で心を奪われる。平安時代の仮名は彼にとって至上の美しさに感じられた。その後正式に入門し、家庭教師をしてもらいながら指導を受けた。高校は書道で知られる大東文化大学第一高校に進む。その頃から書道展への出品を始め、入選を重ねていった。
「授賞式に行っても仮名部門で入選している若い男の子なんて僕しかいませんでした(笑)」
卒業後はそのまま大東文化大学文学部書道学科に進んだ。日書展(日本書道美術院)や毎日書道展にも毎年出展したが、学費や展覧会への出品料・お手本料・謝礼金の捻出にはいつも苦労していた。
「奨学金はもちろん、30歳までアルバイトや書道講師・教室運営との掛け持ちです。塾の先生、引っ越しやごみの収集。暑い盛りのごみ収集はきつかったなあ。服に一滴でも生ごみの汁がつくともう臭くて収集車に乗せてもらえないから、延々後ろを走るんです。体力はつきましたよ」