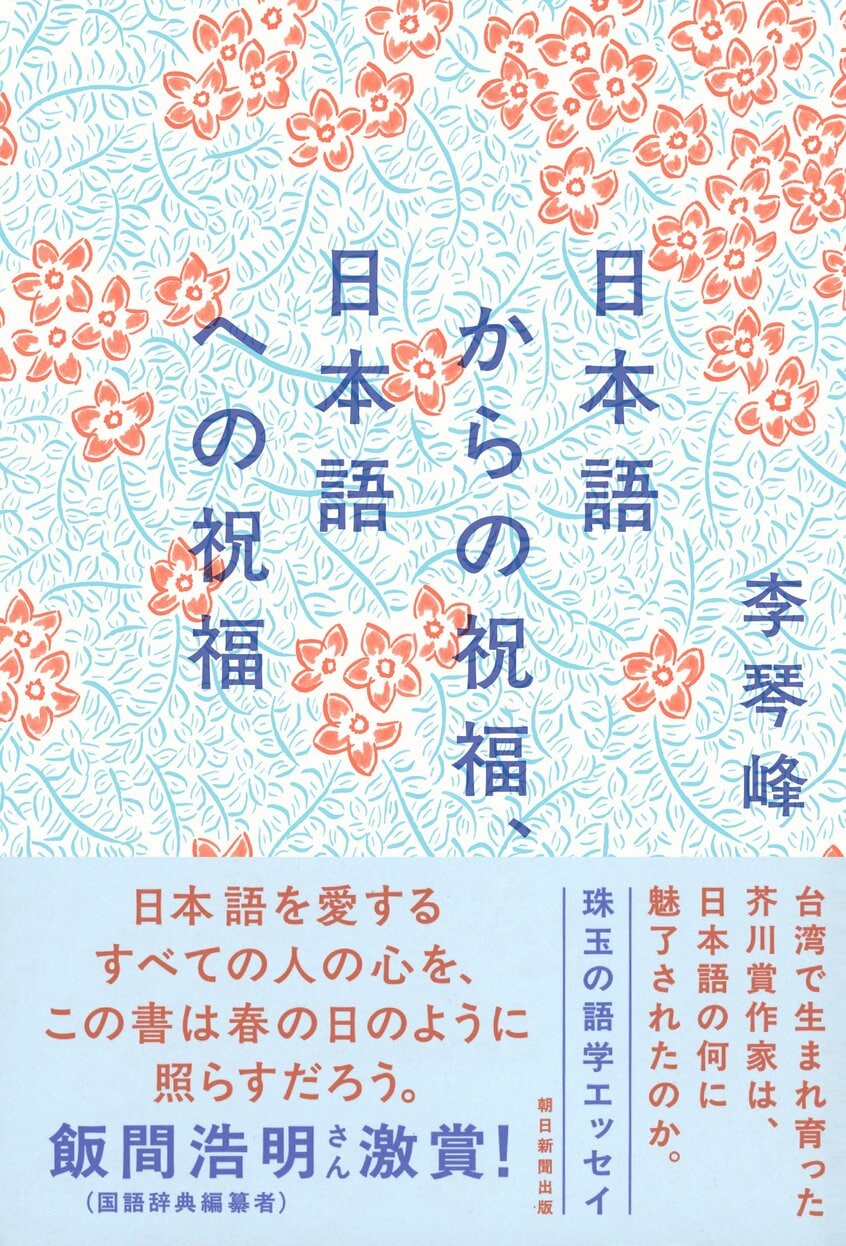
小二のある日、コンビニで売られる新聞の一面の、とある記事の見出しに私は目を惹かれた。その記事の見出しには「口袋怪獣」という四文字が含まれていた。当時私は既にある程度字が読めていたので、「怪獣」というファンタジックな言葉に注意が向いたのだ。「口袋怪獣のパワーは実にスゴイ! 日本中の子どもを襲撃!」みたいなノリの見出しだったと記憶している(台湾の新聞記事の見出しは何かと扇情的だ)。何だろうと思って本文を読むと、どうやらアニメのせいで日本ではたくさんの子どもが病院送りになったらしい。
「口袋」とは「ポケット」のことで、「怪獣」は当然「モンスター」だ。この記事はつまり、1997年12月16日に起きた「ポケモンショック」を報じるものだったのだ。当時日本で放送された『ポケットモンスター』第三十八話「でんのうせんしポリゴン」では激しい光の点滅が多用されたため、子どもたちは光過敏性発作を起こし、身体に不調を来たした。あの時『ポケットモンスター』は台湾ではまだ放送されていなかったので、記事を読んだ私は「へー、すごいアニメだなー。怖いから見ないでおこう」くらいの感想しか抱かなかったと思う。
しかし果たして、『ポケットモンスター』が『神奇寶貝』というタイトルで台湾でも放送が始まると、私はすぐにハマってしまった。これが日本の子どもたちを病院送りにしたあのアニメだとも気づかずに。
それもそのはず、「神奇寶貝」と「口袋怪獣」では、語感がまるで違う。恐らく「ポケモンショック」の時、台湾ではまだ正式な訳名が存在していなかったので、新聞記者は「ポケットモンスター」を「口袋怪獣」と直訳したのだろう。ところが台湾での放送開始にあたり、より子どもにとって親しみやすいタイトルが必要ということで、「神奇寶貝」というタイトルがつけられた。「神奇」とは「不思議な」の意味で、「寶貝」とは「宝物、ベイビー、可愛い子」という意味なので、なるほど確かに子ども向けアニメに相応(ふさわ)しいタイトルと言える。『神奇寶貝』が台湾でも大流行したためだろう、『デジタルモンスター』が台湾に輸入された時もその訳し方を踏襲し、『數碼寶貝』というタイトルになった。


































