執筆当時は唯の視点で書いていて、大人の泉にも弱い部分があるのだと認めてしまうと、彼は自分にとって安全な人でなくなってしまうから、弱いところを見ないように、自分から進んで盲目になる様子を書いていました。もちろん大人の自分として、成人男性の元に通う少女を書いているという自覚はあったから、その塩梅も気にはしていました。
三宅:その意味で、唯と泉の関係はファンタジーではあるけれど、シェルターが必要な子供は絶対に居るから、今の時代にこういう物語があってくれることに希望を感じます。
佐原:家庭や学校で発生する悩みを、そこで解決する必要はないんですよね。学校で発生した悩みを学校で解消する必要はないし、家庭で発生した問題を家庭で解消する必要もない。別のところで解消してもいいし、むしろそうした方がいいんじゃないか、と考えながら書いていたように思います。
三宅:これまで小説では書かれなかったような、食への拒否反応を示す描写も印象的です。
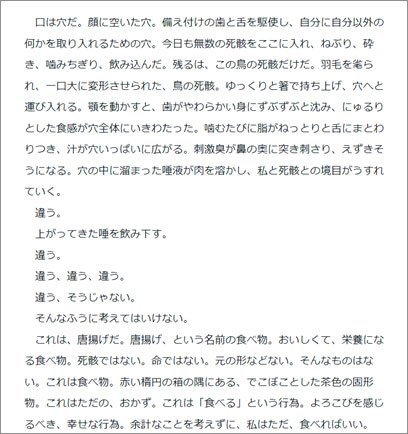
佐原:ひとつの行為に対して絶対正義は無いはずなのに、食べるという行為に対しては、それが絶対的にポジティブなものとしてまかり通っているという感覚があって、それがこの小説に反映されていると思います。昔から私自身ができないものが多くて、唯一できるのが勉強、それ以外はポンコツで生きてきた。できる人にとってはできないことって見えないから、できないところに光を当てたいと思っていたところに、編集者から食について書いてみませんかという話が来たので、あまり食べられない私と思って、じゃあ書こうかなって。
できないことができるようになったり、弱いものが強くなったり、そういう「成長」こそが物語の正義みたいに言われがちじゃないですか。でもそれだけじゃないはずだということも書きたかったんです。「できない」を「できる」にするじゃなくて、できない自分とどう生きていくか、「できない」をどう人生に組み込んでいくのか。だから、まずは自分が自分の味方になってあげられるように、そんな小説を書きたかった。
三宅:佐原さんご自身はできないことをどうやって受け入れてきたんですか?
佐原:私はできないですよって最初から言うようにしてますね。もっと明るく言っていいと思うんですよね。『おら、東京さ行ぐだ』って曲あるじゃないですか。あの曲の「テレビもねえ!」ぐらいの明るさで「できない!」って言っていいんじゃないかなって。言葉にしたからって伝わるとも限らないんですけれど、そもそも言葉にしないと自分の状態って伝わりようがない。みんな違う身体だから、痛みやその程度も分からないんですよね。想像にはやっぱり限界があるから。


































