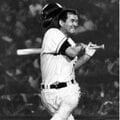場を重ねるうち「記憶の継承とは何か?という根本の問い返しができる」と思ったのが本にした動機だという。
「記憶の継承というと、語り部のように個の体験の語りを継承してゆくものと考えがち。でも自分の体験ではないことをどう継承する? まずはそこを根本的に問い直そうとする山内館長の意図がありました。〈モノ〉を介した記憶の共有回路のつくり方があると気づいた時に、ワークショップも成立したんです」
本書は被災物を介した応答の試みが、姜さんの語りとともに展開する。ワークショップ参加者のモノ語り集には、阪神・淡路大震災の経験と重ねたり、子どもの頃の記憶とつなげたり、身体で表現したりといろいろな応答が綴られている。参加者からは「これまで誰にも語らなかった記憶が噴き出した」という。
「記憶の芯には感情がある。その感情が記憶のつなぎ目になる。経験は違っても互いに流れる感情でつながろうとするのは、日常で誰かの大切な話に応答する時と同じ。記録とは違うレベルで、感情を共有する記憶継承の仕方があっていい」
応答の過程を見つめる中で、こんな気づきもあった。
「私たちは目に見えない何かの力に気兼ねして、言いたいことを実は言わずに生きてるねって。特に大災害の後には、復興の物語が大声で語られる一方で、個々の小さな記憶が表に出ない。みんなが自分の記憶を型にはめることなく語り始めた時、世の中は変わる。私たちには物語る場が必要」
小さな声の場を開く実践でもあったという被災物ワークショップ。たくさんの声が重なるこの本を読むうちに、自分のモノ語りがはじまるかもしれない。
(ライター・桝郷春美)
※AERA 2024年4月1日号