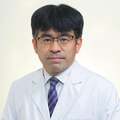梅毒は性交や母子間で感染する。感染部位と粘膜や皮膚の直接の接触によるもので、男性器にコンドームをつければ感染しないというものではないが、そもそも男性器を洗わず(というか体すら洗わず)行為することがサービスと捉えられていたり、洗っていない男性器をすぐに口に含むことに価値が持たれたりしているような日本の性産業“文化”で、買春者の相手をする女性たちの健康はおびただしく脅かされている現実がある。
にもかかわらず、梅毒増加の報道などから感じるのは、「20代の女性たちの性意識・危機意識の変化」を求めるような姿勢だ。母子感染が脅しのように使われ、将来母体になる可能性のある身として、リスク回避を若い女性たちに求めている報道側の意識をうっすらと感じるとき、私も冒頭の女友だちのように机をバンッと叩いて叫びたくもなる。なぜ、男たちの買春文化は問わずに、女たちの性行動や性の価値観を問題にするのか。いったいこの種の悔しさを、私たちはいつまで強いられるのだろう。
日本の女性運動と性病の関係は深い。
日本初の公認女性医師となった荻野吟子は、遊郭に通う夫に淋病をうつされた。当時は女性の医師はおらず、買春夫から感染させられた女性たちの中には医師の診察を拒み、そのために健康を害し、命を落とす人もいた。遊郭の女性たちも性病には苦しめられ、その寿命は明らかに遊郭に閉じ込められていなかった女性よりも短かった。荻野吟子は、そういう女性たちのために、当事者の女性として医師免許を取得した。戦前は日本は世界で最も女性医師の多かった国の一つだ。今年120周年を迎える日本女医会は世界最古の女性医師会だが、女に人権がなく、男が女を買うのは当たり前の社会で、この国の女性たちは当事者として医師を目指したのだ。
また、日本最古の女性の会である矯風会は、一夫一婦制を求めた。今となっては古い価値観と笑う人もいるが、妾を囲うのは男の甲斐性、遊郭で遊ぶのが当たり前という時代に、夫にも純潔を求める思想は当時「新しかった」のだ。そもそも、「万世一系」を「誇る」天皇家も、側室(妾)という存在がなければ存続できないものだった。明治時代の女性たちが一夫一婦制を求めるということは、天皇制にも抗う思想だった。
あの平塚らいてうも、買春社会と闘った。自分の意思では結婚も離婚も許されない時代、夫から梅毒をうつされ子どもを産めなくなった女性たちが離縁されるのは珍しくなかった。らいてうたちは、結婚時に性病検査を男に求める運動を起こしたのだ。