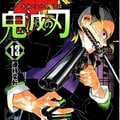原油価格上昇がガソリンや電気料金などの値上がりを招き、8月から家計を直撃。そこに記録的な猛暑が加わって野菜などの食料品も高騰している。そして乳製品も……。
* * *
政府・日銀が全力を尽くしても上がらなかった日本の物価がこの夏、突然上がり始めた。原因は原油価格の上昇と猛暑だ。
原油高はガソリン価格の上昇に直結している。レギュラーガソリンの店頭価格は8月20日現在、全国平均で1リットル当たり151円90銭。昨年のこの時期を20円ほど上回る(石油情報センター調べ)。マイカーでの遠出を控えるなど、消費への影響が顕著になる150円の節目を上回る水準だ。都内のガソリンスタンドでは160円前後まで上昇している。
この8月は電力10社がすべて電気料金を値上げし、標準世帯で13~37円の負担増に。東京ガスなど都市ガス大手4社も値上げを決めた。日本航空と全日空の国際線の燃油サーチャージは8月1日発券分、北米便など主要路線で1万500円から1万4千円へ跳ね上がった。いずれも原油高の影響だ。
原油価格の国際指標である中東ドバイ原油は2017年6月に約46ドルだったが、今年6月には77.41ドルまで上昇している。第一生命経済研究所の永濱利廣首席エコノミストが言う。
「米国によるイランの核合意離脱による供給不安が原因として挙げられていますが、最大の要因は世界経済の好調です」
国際通貨基金(IMF)が7月に公表した世界経済見通しでは、18年と翌19年にそれぞれ3.9%の経済成長が予想されている。「今秋以降も需要は衰えず、原油価格の上昇圧力は強いままでしょう」(永濱氏)
永濱氏の試算では、ドバイ原油が70ドルを超えると、ガソリン代や発電に必要な石油・ガス価格の上昇で日本から2兆8千億円が流出。消費税を1%引き上げるのと同じ打撃になる。
「エネルギー価格が上昇すると、可処分所得の減少をカバーするために衣料品が売れなくなり、自動車や家電といった耐久消費財の買い替えも減ります。家計が自己防衛に傾くので個人消費が冷えこむのです」(同)