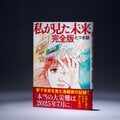「配偶者短期居住権」の制度も4月から始まる。配偶者が自宅を相続できなくても、すぐに行き場がなくならないようにする。遺産分割協議がまとまるまで、最低でも6カ月は住む権利がある。
相続では、すでに変わった点もいろいろある。
遺産分割前でも故人の口座から一定額を引き出せるようになった。法定相続人以外の親族も介護などの貢献分が認められる。結婚20年以上の夫婦なら、配偶者に生前贈与した家は相続の対象に含まれない。最低限の取り分(遺留分)をお金で請求する制度もできた。
大変なのは、亡くなってから10カ月以内に相続税の申告・納付をしなければいけないこと。葬式や片付けなどやるべきことは多く、時間は意外と少ない。
遺産の把握や法定相続人の確定などは手間がかかる。誰がどれだけ引き継ぐかを具体的に決める遺産分割協議はもめやすい。まとまらずに「未分割」の状態でも、10カ月以内に相続税は納めなければならない。期限を過ぎると延滞税がかかる。民法改正でもこうした基本ルールは変わらないので、「相続は時間との闘い」であることを知っておこう。
契約のルールを定める民法の規定(債権法)も新しくなる。債権法は民法が制定された1896年以来、初めて大幅に見直される。消費者保護やインターネット取引への対応なども盛り込まれた。変更点は約200項目にのぼる。
「約120年ぶりの改正で変更点は幅広く、生活への影響も大きい。最近のビジネス基準などに合わせるのと、消費者の権利を守る目的です」(前出の吉田弁護士)
主なものを下記にまとめた。
・借金などの未払い金を請求できる期間(時効)を5年に統一、
・判断能力がない人の契約は無効
・細かい項目全てをわかっていなくても同意があれば契約は有効
・敷金は原則、戻ってくる
・保証人が肩代わりする額に上限を決める
・賠償金などの計算に使う金利(法定利率)が年3%に下がる
(法務省のホームページや取材などをもとに作成)
まず、お金を請求できる期間(時効)は原則5年になる。今までは飲み屋のツケなど飲食費は1年、電気料金は2年、病院の診療費は3年といった具合に、契約の種類ごとに異なっていた。この期間を過ぎると請求できる権利がなくなるため、飲み屋のツケは1年を超えると請求しても払ってもらえない恐れがあった。4月以降は請求できることを知ったときから5年になるため、飲食店側にとっては有利になる。