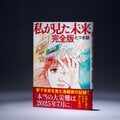ただし、たばこのヤニによる汚れやペットによる傷などは「通常の使い方」にはあたらず、修理代を求められる可能性もある。
借金の保証人を保護するようなルールも導入される。借りた人がお金や家賃を払えなくなった場合に、保証人に請求できる金額の上限を決めておかなければならない。契約書などに金額が明示されていない場合は、無効になることもある。
「部屋を借りていた人の不注意で火事になると、高額の損害賠償を求められるケースも考えられます。これまでは借りていた人の保証人の負担が、“青天井”になることもありました。今回の改正は一般の消費者を保護する狙いがあります」(吉田弁護士)
リスクについて十分に理解しないまま保証人にさせられ、生活が破綻する事例もあった。4月以降に個人が事業用融資の保証人になるには、原則として公証人による意思確認が必要になる。不動産や給与が差し押さえられるリスクなどを理解し、「保証意思宣明公正証書」を作成しないと保証人にはなれない。
「法定利率」も年5%から3%に引き下げられる。滞納金を返すときの遅延損害金や、交通事故の損害賠償額を計算するときなどに用いられているものだ。
いまの低金利の時代では、5%は高すぎるとされ、今後は経済状況に合わせて3年に1度のペースで見直される。
3%になればもらえる遅延損害金は減るが、交通事故の損害賠償額は増える。将来もらえる金利収入である「中間利息」を差し引いて計算するためだ。2%引き下げられれば、それだけ差し引く中間利息は少なくなり、もらえる賠償額は多いケースだと1千万円以上増える可能性もある。
ここまで見てきたように、民法改正は身近な暮らしやお金に関わってくる。ポイントを理解して、損をしないようにしたい。
※週刊朝日 2020年2月7日号