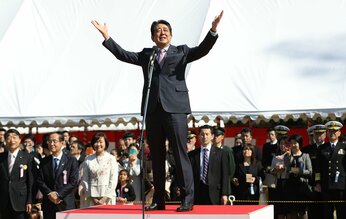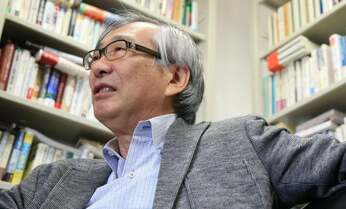「朝日新聞出版の本」に関する記事一覧





その「勉強」はあなたのためになるのか? 無駄な努力を省くために、課題を正しく診断する
ビジネスパーソンの多くは、自らのスキルアップのために、勉強しています。学生と違って、勉強の成果が収入の増減につながるかもしれないビジネスパーソンにとっては、限られた時間のなかで、無駄な「努力」をせずに、効率よく勉強して成果を上げなければなりません。そのためには、自分のしている勉強が正しいものかどうか、常に考えていなければいけません。最近出版された『9割の「努力」をやめ、真に必要な一点に集中する勉強の戦略』(岡健作著・朝日新聞出版)を一部抜粋し、勉強の目的と、現在抱えている課題について把握する重要性を解説します。

特集special feature


「勉強の戦略」を立てれば効率化する まずは「とにかくがんばれ」という呪いからの解放を
勉強をするというと「努力」とか「気合でがんばれ」という言葉がもれなく付いてくると思いませんか? 努力が大好きな人やがんばることが必要だと思っている人には、頑張ってもらうとして、「めんどくさい」とか「努力とか無理」という人はどうしたらいいのでしょう。そんな悩みに応えてくれるのが 『9割の「努力」をやめ、真に必要な一点に集中する勉強の戦略』(岡健作著・朝日新聞出版)です。筆者の岡健作さんは「努力」が大の苦手。その岡さんは効率的に勉強するために「勉強の戦略」を立てます。そのノウハウを同書の一部を抜粋、再編集して解説します。

目の前にゴミをポイ捨てされても黙って掃除を続ける 世界一清潔な空港の清掃人の矜持
今年の夏も暑い。とても暑い。そんななか、エアコン掃除をしてくれる方がいる。ゴミ収集をしてくださる方がいる。昼夜を問わず、介護をしてくれる方がいる。日本中どこまでも、荷物を運んでくださる方がいる。その仕事をしてくださっている人たちに敬意を払う、そんな「あたりまえのこと」ができているだろうか? 仕事って何? 誇りって何? 夏休みを前に、親も子どもと一緒に考えたい。そこで、8年連続清潔さ世界一の羽田空港を支える凄腕清掃人・新津春子さんの著書『世界一清潔な空港の清掃人』(朝日文庫)から、新津さんの心温まる言葉を、一部抜粋・改編して紹介する。


「めんどくさがり」でも勝てる! 努力が苦手な人でもぐんぐん力が付いてくる「勉強の戦略」
DXやらChatGPTやらで、リスキリングやリカレント教育など学びなおし、社会人になっても相変わらず勉強に追われる日々を過ごしている人、結構まわりにいませんか? 学問に王道なしとか、努力は必ず報われるとか、努力に勝る天才なしとか、右を向いても左を見ても、努力、努力のオンパレード。でも努力をすればほんとに報われるんですか? 『9割の「努力」をやめ、真に必要な一点に集中する勉強の戦略』(岡健作著・朝日新聞出版)では努力が苦手な人が、どう勉強していくかという“戦略”を詳しく解説しています。同書を一部抜粋、再編集して紹介します。