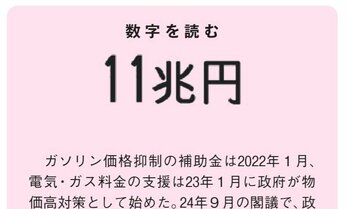パリコレ経験者「ダイヤモンドの原石のよう」 障害がある人とともに目指す「プロモデル」の新境地
モデルの岩下絢音(あやね)さん(25)。モデルを始めて生活様式が変わったという(撮影/写真映像部・和仁貢介)
障がいのある人たちが、プロのモデルをめざして日々努力をしている。パリ・コレクションを経験した元モデルの高木真理子さん(61)が代表を務める、グローバル・モデル・ソサイエティー(GMS)は、障がいがある人たちが所属するモデル事務所だ。
* * *
人と交流し、笑顔が増えた
背筋をまっすぐに伸ばし、ほほえみながら振りむく。装いとたたずまいにはモデルならではの華やかさが漂っていた。
「ファッションやメイクを考えるのが楽しいです」
しっかりとした口調で話すのは、岩下絢音(あやね)さん(25)だ。外見でわかりにくく「見えない障がい」と呼ばれる、知的障がいがある。モデルの活動を始めてから、生活様式が大きく変わった。
もとは家にこもりがちだった。母親は以前との違いについてこう話す。
「引っ込み思案で、人形を持ち歩いて話しかけていることもありました。今は撮影やレッスンに取り組んで、人と交流するようになり、笑顔が増えました」
グローバル・モデル・ソサイエティー(GMS)代表の高木真理子さん(撮影/写真映像部・和仁貢介)
創作活動の幅広げたい
健康のためにウォーキングレッスンを受けたのをきっかけに、2022年からGMSに所属し、ファッションモデルとしての活動を始めた。注目されたりするのが楽しいと感じるようになった。撮影のたび、髪形や服装を変え、リクエストに応じてポーズをとる。
あいさつやコミュニケーションもモデルの活動に合わせて見直してきた。
「つい、好きなことをたくさん話してしまう」(絢音さん)ため、「何をどれだけ話すか」について、母親に相談することもある。
ファッションやメイクを研究し、歌やダンスのレッスンも受け、演劇の舞台も経験した。布に染料で色をつけ、糊付けやコテ当てをしながら造形するアートフラワーでアクセサリーも制作する。
モデルに加え、多様な表現や創作活動の幅を広げて、将来はアーティストとして活動するのが目標だ。
障がい者のための「モデル枠」ではなく
「障がい者のための特別なモデル枠ではなく、障がい者が健常者と同じようにモデルの職業を選べる社会をめざしたい」
こう話すのは、障がい者を集めたモデル事務所、グローバル・モデル・ソサエティー(GMS)代表の高木真理子さん(61)だ。
パリコレの出場経験もある元ファッションモデルの高木さんは、一般の人向けのウォーキング教室を主宰してきた。「知的障がいがある子どもたちに指導してほしい」と頼まれたことをきっかけに、親子で参加できる知的障がい者向けの教室を開催している。
モデルとしてレッスンに励む(撮影/写真映像部・和仁貢介)
ふつうに接し、率直に伝える
懸命に歩き方を学ぼうとする障がいのある子どもたちと接し、親たちの悩みを聞くうちに、高木さんは疑問を持つようになった。
「障がいがあるからできないと、本人もまわりも決めつけている。障がい者にどう接していいのかわからないから、はれものにさわるような対応が多いのではないか」
高木さんは、障がい者を持つ子どもにも「ふつうに」接し、気が付いたことは率直に伝えている。知的障がい者が社会人としてTPOに合わせたふるまいやコミュニケーションができなければ、目をつぶることなく、時間をかけて教えている。
「箸やフォークが使えるのに手づかみで食べる子もいました。教えたら、しっかりできるようになりました」
ほほえむ岩下さん。所作の一つ一つも美しい(撮影/写真映像部・和仁貢介)
モデルの素質をみたうえで
障がいがある子どもたちが成長する姿は「ダイヤモンドの原石のようだった」(高木さん)。GMSを22年に創設した。知的障がい、ダウン症、遺伝性疾患、身体障がいなどさまざまな障がいのあるモデルが所属している。
「健常者と同様に、障がい者もモデルになれる人の数は限られている」と高木さんは説明する。GMSには障がいがある人から「どうしたらモデルになれるのか」と数多くの問い合わせがある。モデルとしての素質をみたうえで、本人の努力や家族の協力も必要になるため、実際に可能性に向けて挑戦できるのは1~2割だ。
親の協力も大切だ。テーブルマナーや身だしなみを「日常生活から意識するように」する。鏡をよく見て、ヒールを履き、化粧をする。白い服を着て食べ物をこぼさないようにする、良質なものを身に着けるといった「見られている」存在であることを認識する。自分をアピールし、気持ちを変えるファッションの力をいかす。
「撮影を通して主役としての場を持つことで、個性が磨かれ輝きが増していった」(高木さん)
口角を上げるトレーニングや歩き方など、必要に応じてワークショップを開くことはあるが、モデルになるためのレッスンは常設していない。個人がそれぞれトレーニングをしている。
明るいまなざしが印象的な清野優里さん(撮影/写真映像部・和仁貢介)
「好き」「やってみたい」
大きな瞳を輝かせ、人なつっこい笑みを浮かべるモデルの清野優里さん(31)。染色体異常のひとつで小児慢性特定疾病に指定されている4pマイナス症候群がある。視力が弱い、成長障がいがある、精神や言語の発達が遅れるといった特徴があり、5万人に一人といわれる障がいだ。
以前の優里さんは「暑さや寒さに弱く、体調管理のために家から出ないことも多かった」と母親は話す。高木さんのウォーキングレッスンを受けるようになって数年間が経ち、体幹が強化されて歩き方や歩幅が広くなり、長い時間歩けるようになった。
モデルを始めたきっかけは、本人が興味を示したことだった。自分から言葉を発することはなくても、「好き」「やってみたい」と母親に意思を伝えてきた。撮影の場でも、楽しそうにいきいきとしている。外出が増え、体が丈夫になった。
もとから「明るく、緊張しない」(母親)という優里さんの強みが、舞台の演技でも発揮された。24年5月に日本舞踊家の月妃女さんが主宰する演劇『台湾に命を捧げた八田與一の半生』に子ども役の一人として出演し、物怖じせずに喜びや悲しみを豊かな情感で表現した。
今後はミュージカルに挑戦するため、歌のレッスンにも励んでいる。
清野優里さん(撮影/写真映像部・和仁貢介)
ありのままの姿で舞台に
障がいがある人がモデルとして活動する機会は広がりつつある。
「時代とともに、より多様性、個性が認められるようになっている」と、高木さんは説明する。モデルはファッションや商品のよさをアピールする役割で、人としての個性を前面に出すことが求められているわけではない。しかし、時代とともにモデル像は多様化している。
「私がモデルをしていた1980年代は歩き方の美しさが求められ、マネキンのような立ち位置で、笑うことさえ許されなかった。90年代から笑ってもよくなり、今は歯に矯正器具がついていてもいい、ありのままの姿で舞台に立てるようになった」(高木さん)
欧米では障がい者やトランスジェンダーなど性的マイノリティーのモデルもプロとして活躍している。日本ではまだ「障がい者としての枠組み」での起用はあっても、健常者と同じ立ち位置でモデルをめざすのは難しい状況だ。
「障がい者を採用してお金もうけをしているのかと批判が来たこともある。福祉の役割は大切だけれど、障がい者は『何かをしてあげる』だけの対象ではない。モデルをしたい人がいるならば、仕事として収入を得られる環境にしたい」(高木さん)
(ライター・斉藤真紀子)