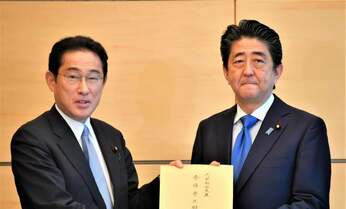公文書改ざん問題で、自死した赤城俊夫さんの苦悩を、妻・雅子さんが無念とともに明かす
森友文書改ざん問題で記者会見に応じる赤木雅子さん
今年9月、森友学園への国有地売却をめぐる財務省の公文書改ざんを関与させられ、自死した近畿財務局の赤木俊夫さんの妻・雅子さんが、元理財局長の佐川宣寿氏に賠償を求めた訴訟は、佐川氏らへの尋問を認めず結審した。小塚かおる・日刊現代第一編集局長が、俊夫さんの苦悩と雅子さんの無念を綴る。朝日新書『安倍晋三 VS. 日刊ゲンダイ 「強権政治」との10年戦争』から一部を抜粋、再編集して紹介する。(肩書は原則として当時のもの)
* * *
【あわせて読みたい】
#1 安倍晋三元首相の経済政策がのっけから躓いた当然の理由
#2 貧しい国、人権も尊重しない国に外国人は住みたいか
#3 防衛相がこぼした「安倍さんが約束しちゃったから」
#4 「軍備の増強と、使わない外交を」梶山静六の言葉の重み
#5 公文書改ざん問題で自死した赤城俊夫さんの苦悩を、妻・雅子さんが明かす
#6 安倍政権の「国会軽視」を加速する岸田首相 自民党の謙虚さはどこに
#7 「3年間、抱っこし放題」で女性が喜ぶと疑わなかった安倍首相のズレの根深さ
#8 「夫が働き、妻は家で子育て」古い価値観に固執する自民党
#9 「女性ならではの感性と共感力」で漏れたオッサン政治の本音
#10 勝率“8割”世襲議員に国民の苦しみは理解できるのか
銃撃の2日後、赤木雅子さんとの電話
「亡くなる前日に、安倍さんに会って手紙を渡したんです」
赤木雅子さんから連絡をもらったのは、安倍晋三氏が銃撃された2日後だった。
雅子さんは、森友学園問題で財務省の上層部から指示された公文書改ざんに苦しみ、自ら命を絶った近畿財務局職員、赤木俊夫さん(享年54)の妻。取材を通じて私は交流がある。
雅子さんとは銃撃当日の夜にも電話で話していた。突然のことで、衝撃は大きかった。
「こんなことが起きるなんて」と少し動揺した様子で、2、3分短く会話して終わっていた。
2日後は別件で連絡をもらい、その会話の流れで、「安倍さんに会った」という話を聞いた。その日の電話口の雅子さんは落ち着いていた。
【こちらもおすすめ!】
安倍政権の「国会軽視」をさらに加速する岸田首相 「野党に7割の配慮をする」自民党の謙虚さはどこに
「参院選の応援で安倍さんが三宮(神戸市)に来られて。たまたま当日の昼に三宮を通りがかった時に、その日の夕方に来られるのを知り、喫茶店で手紙を書いて持っていったんです」
「でも、1000人ぐらいが集まっていて、とても手紙を渡せるような状況ではなくて。もういいや、と諦めていたら、演説を終わられた安倍さんが聴衆の中に入ってグータッチを始めた。そして、偶然こっちに近づいてきたので、私も安倍さんとグータッチをして、『手紙を書いてきました』と言ったら、安倍さんは『えー、手紙』って大きな声を出して。SPの人が受け取ります、と」
「手紙には『私はこういうものです。再調査をして下さい』とだけ書きました。SPの人が中を見たら赤木雅子だとわかるので、安倍さんには伝わらなかったかもしれませんが……。そうしたら翌日……。手の温かみを感じたばかりの人が……。本当に驚きました」
雅子さんは、夫がなぜ自ら命を絶たなければならなくなってしまったのか、公文書の改ざんは誰の命令だったのか、「真実が知りたい」と裁判を起こして戦っている。
「真実」は当事者である安倍氏が存命の時に明らかにされるべきだった。
偶然が重なり、雅子さんが手紙を渡せたのはよかった。でも……。
【あわせて読みたい】
「軍備の増強と、使わない外交をセットで」 “軍人”梶山静六が残した言葉の重み
「残念です。もう再調査できないというか、再調査をして下さいと訴える相手が1人いなくなってしまいました。国会で『私や妻が関係していたら総理大臣も議員も辞める』とおっしゃったことがきっかけで財務省の公文書改ざんが始まったのは間違いないと思うので、その原因を作った当事者がこの世からいなくなるのは残念です」
俊夫さんの苦悩、雅子さんの無念
私が赤木雅子さんと初めて会ったのは、夫・俊夫さんの自死の真相解明を目指して国と佐川宣寿元財務省理財局長を提訴した民事裁判が始まった頃の2020年夏だった。
その年の3月に俊夫さんの残した遺書と財務省による改ざんを告発する手記をスクープしたジャーナリスト・相澤冬樹氏が、ゲンダイで雅子さんの「法廷闘争記」をスタートさせていたこともあり、直接会って、インタビューをする機会を得た。
雅子さんは名前こそ実名で取材に応じているが、顔出しはNG。初めて会った際の印象は、「こんな華奢な女性が1人で国を相手に戦うのか」という感慨と同時に、雅子さんの語る言葉が自然体かつ当たり前の庶民感覚から発せられるものばかりで、国家やエリート官僚機構という巨大権力との対比をより感じさせ、強い怒りが込み上げてきた。救われたのは、雅子さんが「キャッ、キャッ」と声を出して笑うようなとても明るくユーモアのある女性だったことだ。
【こちらもおすすめ!】
防衛相がこぼした「安倍さんが約束しちゃったから」 米から武器を爆買いしたツケの「兵器ローン」
「私の趣味は赤木俊夫」と公言するほど、雅子さん夫婦は仲がよかった。あんな不幸がなければ、今も当たり前に2人で幸せに暮らしていただろう。財務省職員は誰一人、起訴されることはなかったが、公文書改ざんは犯罪行為だ。公務員として絶対にやってはならないし、マトモな感覚ならやらない。だから、俊夫さんは苦しんだ。
「近所の方に『僕の雇用主は国民です。国民のために誇りを持って働いています』ということを恥ずかしげもなく表現する人でした」
インタビュー時に雅子さんは、俊夫さんが肌身離さず持っていた「国家公務員倫理カード」を見せてくれた。クレジットカード大の大きさで、ずっと持ち歩いていたからシワができ、文字や色もかすれていた。
カードには「倫理行動規準セルフチェック」として5つの項目が書かれている。
・国民全体の奉仕者であることを自覚し、公正に職務を執行していますか?
・職務や地位を私的利益のために用いていませんか?
・国民の疑惑や不信を招くような行為をしていませんか?
・公共の利益の増進を目指し、全力を挙げて職務に取り組んでいますか?
・勤務時間外でも、公務の信用への影響を認識して行動していますか?
雅子さんがインタビューで吐露したのは、安倍首相、麻生太郎財務相、佐川元理財局長そして財務省の面々は「どこを向いて仕事をしているのか」という疑問だった。働いていた大学生協で商品のポップにイラストをつけていたほど似顔絵が上手な雅子さんが描いた安倍氏ら3人には、「黒目」がなかった。どこを向いているのかわからないからだ。
【あわせて読みたい】
〈この国の首相はアホかホラ吹きか〉安倍晋三元首相の経済政策がのっけから躓いた当然の理由
中でも、財務省の組織の論理と保身は異様だった。雇用主は国民ではないのか? どこを向いて、誰のために働いているのか? 雅子さんの話を聞けば聞くほど、「財務省職員よ。もう一度、倫理カードを読み返せ」と叫びたくなった。
2020年8月13日発行のゲンダイからインタビューを一部抜粋する。
──俊夫さんのお葬式で近畿財務局の人たちが記帳しなかった、というのにも驚きました。
義理の姉から「雅子ちゃん、おかしいよ。記帳してくれなかったのよ」って言われて、「えーっ」となって。以前所属していた中国財務局は、来てくれた代表の人が住所も書いた名簿を渡して下さったんですけど、近畿財務局は誰ひとり記帳もせず。跡を残したくなかったんじゃないかと思います。
──酷い組織ですね。本(『私は真実が知りたい』(文藝春秋)相澤冬樹氏との共著)でも、「嫉妬深い男社会」「男ってつまらんな」って。
財務局の人が家に来て、帰られた後、「私は生まれ変わっても絶対に女に生まれたい」というのが一番の感想だったんです。なんか、へこへこしていてつまらない、って。
──へこへこ。どういう状況ですか?
(近畿財務局の)局長がお付きの人2、3人と共にやって来て、「赤木君はこういう人だった」って褒めてくれるんですけど、お付きの人が首を上下に振るんですよ。特に一番首を振る人は、しゃべる時に私ではなく、局長を見てしゃべるわけです。何しに来たんやろって思うくらい。そして、局長が「麻生さんのお墓参りを断ったそうだね」「うん、よしよし」ってことを言われて。
──うん、よしよし?
私が黙ってて意思を出さないから、「それでいいんだよ。それなら公務災害を認めてあげるからね」っていう空気をバンバン出してました。まさか私が裁判をするなんて想像もしていなかったと思います。
──自死した遺族に、そんな対応なんですか。
どこまでも組織の一員として扱われるんです。「あなたはこのランク」と、家族も組織の中の夫のいる場所に入れられる。
【こちらもおすすめ!】
安倍政権の「国会軽視」をさらに加速する岸田首相 「野党に7割の配慮をする」自民党の謙虚さはどこに
請求を受け入れて「臭いものにフタ」
亡くなる前の俊夫さんは、「これは戦争と同じで、上司に指示されれば、白いものを黒と言わなきゃいけない」とまで言うほど追い詰められていたという。犯罪行為に対しては、民間企業以上に清廉潔白であるはずの官僚組織のモラルが、なぜそこまで堕ちてしまったのか。
安倍政権時に「内閣人事局」ができたことなどで官邸主導の恐怖人事が行われ、イエスマン官僚や忖度が広がった。官僚は「何が正しいか」ではなく、安倍首相にとって「何が都合がいいか」を探し、政権にシッポを振るようになっていったのだ。
赤木雅子さんの裁判は、2021年12月、国側が突如「認諾」を申し出て、強制的に終わらせた。原告の請求を丸ごと認めて賠償金を支払い、裁判を終結させたのである。
いよいよ関係者が証人として呼ばれる可能性が│という段階だったのに、国側はそこから逃げ、幕引きを図った。
「認諾」された翌日、雅子さんは夫・俊夫さんにこう報告したと私に話した。
「謝りました。ごめんね、としか言えなくて。ごめんね、こんな結果にしてしまいました、と伝えました」
【こちらもおすすめ!】
安倍政権の「国会軽視」をさらに加速する岸田首相 「野党に7割の配慮をする」自民党の謙虚さはどこに
雅子さん側は、国の認諾を警戒して請求金額を1億1000万円余りにまで引き上げていたが、それでも国側は認諾した。雅子さんが欲しいのは巨額の賠償金ではない。訴訟という形を取るうえで、損害賠償の請求が必要なので金額を設定しただけで、欲しいのは真実を知ることだけだ。
国側には、1億円超を支払ってでも法廷で明らかにされたくない、何かやましい、不都合な事情があるわけだ。国側の最高責任者である岸田文雄首相が安倍氏に配慮し、臭いものにフタをした。
言うまでもなく、国側が支払う1億円は税金だ。真実を“隠蔽”するために通常の国家賠償では考えられないほどの額を支払うのは、国民の納得を得られるものではないし、筋が通らない。
残る佐川宣寿氏との裁判は一審で雅子さん側の訴えが棄却された後、23年9月13日、控訴審が結審した。被告の佐川氏本人は一度たりとも出廷していない。それどころか、「再就職のために裁判を早く終わらせたい」と代理人が主張する図々しさで、雅子さんの心を傷つけてもいる。赤木俊夫さんの死に対する懺悔や後悔の気持ちはないのだろうか。
佐川氏は何のために改ざんを指示したのか。いまだ真実は藪の中だ。
【ほかの回もあわせて】
#1 安倍晋三元首相の経済政策がのっけから躓いた当然の理由
#2 貧しい国、人権も尊重しない国に外国人は住みたいか
#3 防衛相がこぼした「安倍さんが約束しちゃったから」
#4 「軍備の増強と、使わない外交を」梶山静六の言葉の重み
#5 公文書改ざん問題で自死した赤城俊夫さんの苦悩を、妻・雅子さんが明かす
#6 安倍政権の「国会軽視」を加速する岸田首相 自民党の謙虚さはどこに
#7 「3年間、抱っこし放題」で女性が喜ぶと疑わなかった安倍首相のズレの根深さ
#8 「夫が働き、妻は家で子育て」古い価値観に固執する自民党
#9 「女性ならではの感性と共感力」で漏れたオッサン政治の本音
#10 勝率“8割”世襲議員に国民の苦しみは理解できるのか
●小塚かおる(こづか・かおる)
日刊現代第一編集局長。1968年、名古屋市生まれ。東京外国語大学スペイン語学科卒業。関西テレビ放送、東京MXテレビを経て2002年、「日刊ゲンダイ」記者に。19年から現職。激動政局に肉薄する取材力や冷静な分析力に定評があり、「安倍一強政治」の弊害を追及してきた。著書に『小沢一郎の権力論』(朝日新書)などがある。