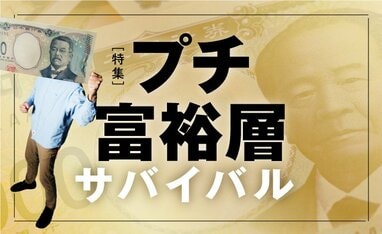一冊の本

7月号ミュージシャン 小宮山雄飛(ホフディラン) Komiyama Yuhiカレーの履歴書
本業はミュージシャンながら、年間200軒のカレー屋巡りと、家でも200食近くカレーを作る僕ですが、カレーとの出会いはちょっと変わっています。というのも僕の家にはいわゆる「おうちカレー」がなかったのです。うちの母は家族の健康を考えて、食卓においてできるだけ自然の素材にこだわり、いわゆる「できあい」のものを使わないというポリシーを持っていました。なので、うちではレトルトや缶詰のカレーが食卓に上がることはなく、カレールゥすら使わない主義でした。といって、インド料理の知識があるわけでもない母が、ルゥを使わずに一からスパイスを調合してカレーを作るなんてのは不可能。その結果、母はカレーに関してとてもシンプルな結論に達しました。


6月号作家 市川拓司 Ichikawa Takuji「障害」を進化的戦略と考える
前作『壊れた自転車でぼくはゆく』から一年半ぶりの新刊です。今回は小説ではなく初めての新書。けれど思いは一緒です。傷むほどに感じてしまうために「弱者」と呼ばれ、独自の価値観で生きているために「間違っている」と糾弾されてしまう者たちの真実。それをフィクションではなくノンフィクションで描く。ぼくの中では、あまり違いはありません。ぼくの小説を読んだ方なら、「ああ、わたしは彼を知ってる」と思われるかもしれない。すべての小説に登場する主人公や脇役たちの原型がここにある。彼(すなわちぼく)は『いま、会いにゆきます』の巧や佑司であり、『そのときは彼によろしく』の智史であり、『壊れた自転車でぼくはゆく』の寛太でもある。ぼくはなぜ、あのような主人公たちの物語を書いたのか? というより、書かざるをえなかったのか? その理由が徐々に明かされてゆきます。執筆しながら新たに学んだこともたくさんありました。すべては無意識のなせるわざですが、その背後には「コンプレックスPTSD(心的外傷後ストレス障害)」という深い心の傷がありました。発達障害であること、アスペルガーやADHD(注意欠陥多動性障害)であることと同じくらい、ぼくのパーソナリティーに大きな影響を与えた子供時代の体験。病弱な母がまとう死の影に怯えながら暮らした日々。それが、いずれはパニック障害を引き起こし、数々の心身症を引き起こす原因のひとつとなっていく。けれども、この日々はまた、ぼくに別の感情も与えてくれました。母の身体を深く気遣うことで、ぼくはいたわりや共感の心を育むことができた。ぼくはこの感情をとても大切に感じています。気遣い、いたわること。あまりにもその感情が強すぎるために、実際以上に相手が脆く儚(はかな)い存在のように思えてしまう。愛した瞬間から喪失の予感にとらわれ、一秒たりとも無駄にはできないと思うようになる。それこそ傷むように感じるわけです。この激しい感情に促されるようにしてぼくは小説を書き始めました。治癒行為としての執筆。今回の本の中で、ぼくは全体の三分の一ほどをさいて、そこまでの道のりを詳しく綴っています。ぼくを生んだことがもとで身体を壊し臥(ふ)せりがちになってしまった母。そんな母とほとんど二人きりで送った奇妙な幼年期。あまりの多動多弁に、担任の先生から「三十年の教師生活で一番手の掛かる子」と嘆かれた少年期。勉強ができずクラスメートたちから「バカ」とあだなされた思春期。奥さんと出会った高校時代、そしてパニック障害を発症。様々な不具合を抱えながら過ごした青年期。奥さんの妊娠を機に小説を書き始め、それがやがては『いま、会いにゆきます』のミリオンセラーへと繋がっていく。さらには、ぼくの書いた小説が世界の様々な国で翻訳出版され、人種や国境を超えて愛されていったこと。本書の中で、ぼくはこう書きました。「このあまりに攻撃的な世界で、生きづらさを感じている人々。戦うための拳を持たない、生まれながらの避難民たち。弱い者、拙い者。ひとと違っているために、『間違っている』と責められ、自分を信じることができなくなっている者。(中略)そういうひとたちのために、ぼくの小説はあるんだと思います」。それこそがぼくの小説が世界中のひとたちに受け入れてもらえたことの理由なんだと思います。どの国にもぼくの「仲間」はいます。彼らがぼくの小説を求めてくれた。