
一冊の本



12月号美容ジャーナリスト/エッセイスト 齋藤薫 Saito Kaoruお金をかけない“気づき”の美容、そこに人生の好循環が生まれる
この“一冊”は、本のサブタイトルにも、また帯のキャッチにも「気づき」という言葉を使っている。それが何を意味するのか、まずはそこから聞いてほしい。ずばり、ここでの“気づき”には、「お金をかけない」という意味をこめているのだ。たとえば、「人の悪口を言うと老ける」みたいな気づき。「老けない人が太らない」という気づき……。つまり“キレイになること”、また“若くいること”は、本来が驚くほど簡単である事実に“気づくための一冊”であり、だからそれほどお金がかからないことにも、“気づいてほしい一冊”となったのだ。



特集special feature



7月号東京医科歯科大学大学院名誉教授 藤田紘一郎 Fujita Kouichiro「腸内細菌」と「よい水」が認知症を間違いなく遠ざける
私の父は、90歳を超えて初めて認知症を発症しました。三重県の片田舎にある結核病院の院長だった父は、最終的に町の老人病院の勤務医となりました。ある日、「医者だか患者だかわからなくなったので、引き取りに来てほしい」と病院から電話が入りました。家族を全く顧みない自分勝手な父でしたが、認知症になったときは、とても穏やかな好々爺となっていました。父が病院に入院した時は、同室の患者さんを指さし、「あの患者の診察をしなければならないから、カルテを持ってきなさい」と看護師さんに指示していました。そんな姿を見ながら、「ああ、親父は認知症になっても生涯現役を貫いているんだな」と密かに感心してしまったものです。
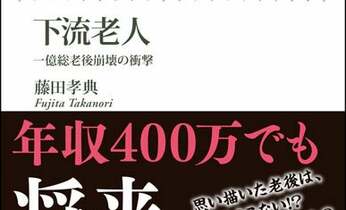

6月号金沢大学助教 日比野 由利 Hibino Yuri世界の現状を見据えた議論が必要
生殖技術の発展に伴い、子どもが欲しいという人々の願望が、以前にも増して膨張してきている。精子や卵子の提供、代理出産、子どもの男女産み分け、受精卵の遺伝子検査や胎児診断など、次々と新しい技術が開発され、これらの技術を組み合わせれば、あらゆる人が子を持つことができる。生殖サービスの顧客は、不妊カップルだけでなく、独身者や同性愛者にも広がっている。インドやタイなど、安価で法的規制が“緩い”新興国で生殖サービスを利用する動きが加速していくにつれて、様々なトラブルが表面化し、経済振興策として生殖ツーリズムを歓迎していた国も外国人による利用を制限する方向に向かっている。

5月号ジャーナリスト 福島 香織 Fukushima Kaori日本の花見文化が思い出させた雪月花を愛でる心
この原稿を書いている今、東京の桜は満開である。千鳥ヶ淵も上野公園も息を呑む美しさで、中国人観光客も大勢訪れていた。知り合いの中国人も、わざわざ桜の開花時期に合わせて日本旅行に来ている。中国にも、桜はたくさんある。それどころか、全世界約150種類の野生種桜のうち中国原産種は50種類以上で、桜の起源は中国だという。日本の桜は、ヒマラヤ山脈あたりの原種が唐代に伝わったものだそうだ。天適集団という中国で初の「桜ビジネス」を展開している企業を以前に取材したとき、そういう話を聞いたし、日本の専門書『桜大鑑』でも桜の原産国は中国とある。なのに、なぜわざわざ日本へ桜を見に?


























