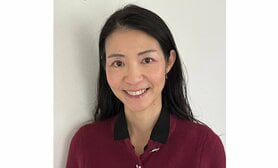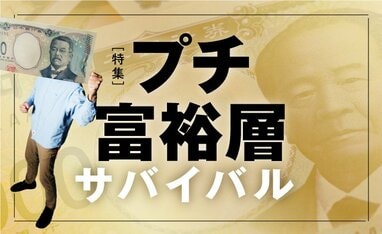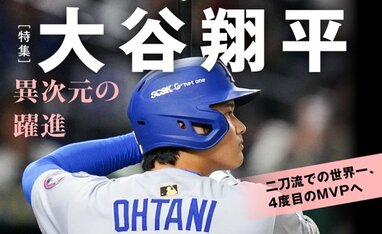一冊の本




4月号装丁家 熊谷 博人 Kumagai Hiroto町人美意識のエッセンス
三重県鈴鹿市は江戸時代から現在も「染め型」の本場。内田勲さんは伊勢型彫り師のひとりで「突き彫り」の第一人者である。無骨な手先はザクッ、ザクッと迷うことなくリズミカルに微細な文様を切り込む。型紙は美濃和紙を3枚、柿渋で貼り合わせ、燻(いぶ)しをしてから1年以上乾燥させて渋(しぶ)を枯らす。手間と時間がかかる日本独自の台紙であり、薄い紙なのに耐水性が強く、伸縮せず、丁寧に使えば数千回の染めに耐えられるほど堅牢だ。型彫りの道具、小刀はそれぞれの職人さんたちが自分で作る。型を彫る時は型紙を六枚ほど重ねるので、小刀は専用の小さな砥石でこまめに研ぐ。根気と集中力、まして、高度な技術が必要だ。


3月号ライター 豊崎由美 Toyozaki Yumi都市への新しい感受性
IngressというスマホやiPhoneで遊ぶゲームがある。レジスタンス(青)とエンライテンド(緑)の陣営が、街の中に存在するポータルと呼ばれるたくさんの拠点を取り合って陣地を広げる、スタンプラリー要素のある位置情報ゲームだ。ポータルに設定されているのは名所旧跡ばかりではない。ヘンテコな看板、オブジェ、小さな地蔵、駅、ビルなどさまざま。現実の道路地図をもとにした画面に点在するポータルを探して歩いていると、「よく知っていると思っていたところに、こんなものが!」という発見があり、新しい街歩きの楽しさを教えてくれるゲームなのだ。白い道を浮かび上がらせた黒い画面に点在するポータルが、青や緑の炎をボォーッと立ちのぼらせる。その仮想現実上の街と、スマホから目を上げた時に広がる現実の光景が重なる感覚は、Ingressが存在する以前にはなかったものだ。都市ばかりが変容し続けるだけではない。そこにいる人間が都市から感受する何かも変わり続けているのだ。
特集special feature

1月号作家 市川 拓司 Ichikawa Takuji「避難民」の物語
昨年の頭にフランスで『いま、会いにゆきます』のペーパーバックと『そのときは彼によろしく』の単行本がほぼ同時に刊行されることになって、あちらの出版社からプロモーションに来てもらえないか? という打診があったんですね。ぼくはこの小説の「寛太」同様、乗り物すべてに対して恐怖症を持っているので、かなりのためらいはあったんですが、それでも、とりあえずは「伺います」と返答しました。でも、いよいよその日が近づいてくると、やっぱりどうにも飛行機には乗れそうになくて、そのことを考えるだけでパニックになってしまい、結局は土壇場で断ってしまいました。一番落胆したのは同行することになっていたぼくの奥さんです。パリに行ける! ってものすごく楽しみにしていたのに、明確な理由(ぼくにとっては明確ですが)もないままにキャンセルですから。ぼくはいつだってこんな調子です。結婚して30年近く経ちますが、関東から出たことなんてほとんどない。旅行にも映画にもコンサートにも行けず、ひととの集まりにもほとんど顔を出さない。そうしていてさえ心や体を乱さずにいることはとても難しい。





11月号東京福祉大学国際交流センター長 遠藤 誉 Endo Homare習近平新政権、完全解剖
「虎も蠅も同時に叩く」をスローガンとして、中国の習近平主席は政権発足後の1年間で18万人以上の腐敗分子を処分した。そのうち15万人は中国共産党の幹部だ。「虎」とは大物の政治家、「蠅」は「虎」のまわりを飛び交う小物たちのことを指す。胡錦濤時代の中央軍事委員会副主席・徐才厚やチャイナ・ナイン(中国共産党中央政治局常務委員9人)の一人だった周永康までが囚われの身となっている。政治局常務委員およびその経験者は政治問題以外の腐敗問題などでは逮捕しないという「聖域」だったが、習近平はその聖域に斬りこんだことになる。