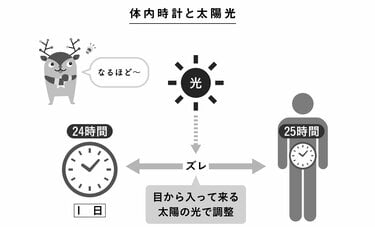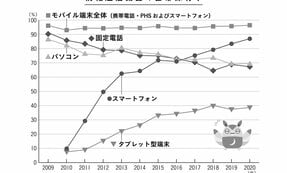■「老い」や「介護」について知っているが、「自分ごと」にできない
ではなぜ、準備不足が起こるのでしょう。そこには、次のような三つの背景があると考えられます。▼情報不足で、老いや介護について想像がつかない▼身近に介護をする人がいないこともあって、「自分ごと」として考えられない▼自分たちの生活がたいへんで親の老後まで考えが及ばない。
情報不足の場合、いくつくらいから老いが始まるか、老いによってどのような心身の変化が訪れるか、どんなことができなくなってどんな危険が生じてくるかなどについて、正しい情報を得ていないために、老いた親に明日、起こるかもしれない事態が想像できません。さらに糖尿病や高血圧症などの親の持病や、高齢者がかかりやすい心臓や脳の血管系の病気、転倒による骨折や熱中症などの病気やケガについての情報も不足していることが多いようです。
最も多いのは、二つめの背景で、「高齢者が要介護になる状況や病気について知ってはいるけれど、うちの両親は元気だから、まだまだ関係ない」と、情報は得ているのに「自分ごと」としてとらえられていないケースです。たとえば親戚のおじさんやおばさんが施設に入所したとか、仲の良い友人の親が倒れて自宅介護になり、友人が介護の毎日でたいへんになっているなど、自分の近くに介護の体験者がいれば、「高齢になった親」がぐっと身近なものになるのですが、そうでなければ「自分ごと」としてとらえるのは難しいのかもしれません。
三つめは、自分たちの生活がたいへんで、親のことを考える余裕がない、というケースです。たとえばパートナーが病気、子どもに障害がある、経済的に余裕がなく働きどおしなどで、高齢になった親という要素が入り込む余地がない場合です。
家族ごとにさまざまな事情や背景があります。どんなケースでも、私たち介護職は、介護を受ける本人や家族が気持ちよく介護生活を送れるように、「急に介護になっちゃった」と半ばパニックになっている家族を、できる限りサポートします。しかし、なかにはやはりひとこと言いたくなってしまうケースもあります。「もっと前に、何度も気づく機会があっただろうに、なぜここまで何の備えもなく来てしまったの?」と。
 高口光子
高口光子