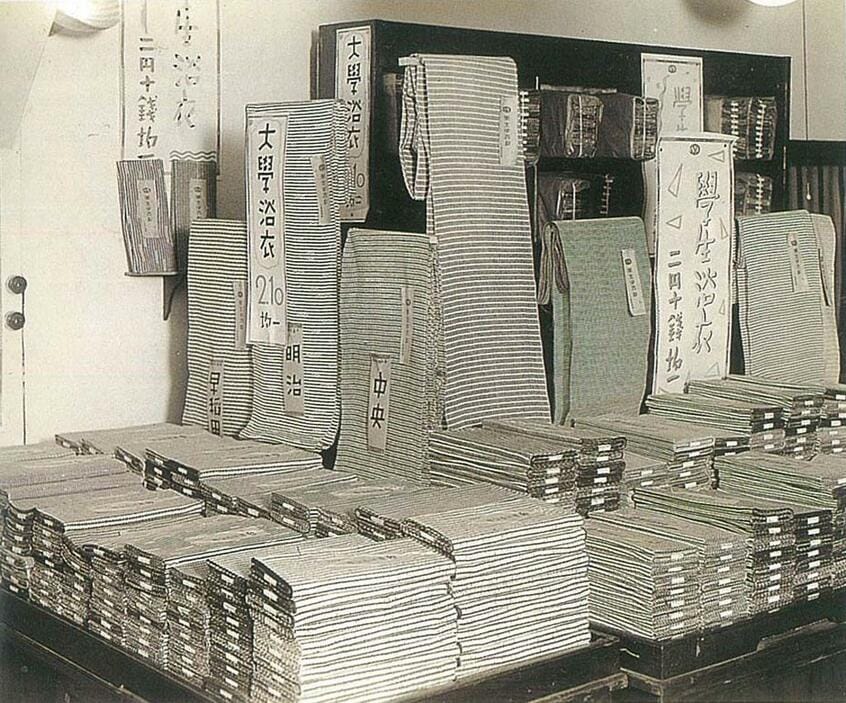
新聞社で写真家・飯田鉄さんの特集を担当していたとき、E・S・ガードナーの文章の一文を引用したいが、記憶が曖昧で調べてほしいと連絡があった。だが締め切りまで2時間ほどしかない。著書は近くの図書館にない。
「そこで、毎日新聞は神保町に近い竹橋にあるので、三省堂書店なら近いし、ここなら必ずあるだろうと思って、走って向かいました。狙いどおりガードナーの著書はあったのですが50冊以上もあり、1冊ずつ目次を見て探しました」
なんとか探している内容に合致する項目が見つかり、その1冊を購入し、全文を読みながら、飯田さんに「これですか」と問うと、「そこだ!」とえらく喜んでくれた。
「三省堂書店を思いついて、膨大な書籍から見つけた自分を褒めてあげたいです。それより著書をそろえていた三省堂書店さん、さまさまですね」
と懐かしそうに話した。
加藤さんが会社を神保町にしたのも、ネットに頼らず自分の目で直接本を見て、本をつくってほしいと若いスタッフに望んでいるからだ。三省堂書店は本をつくるプロにとっても強い味方だ。
本のタイトルや著者がわかっている場合は、店内にある検索機などを使えば探すのは比較的簡単だ。しかし、知りたい分野や読みたいジャンルはわかるが、該当する本であるかがわからないことはよくある。図書館司書のようなサービスを始めたのも三省堂書店だ。
「神保町本店の1階入り口近くにコンシェルジュカウンターを置き、第一線からは退いたが、経験の豊富なベテラン書店員に担当してもらい、こんな本はどこにあるとか、このジャンルならどの本を見ればいいなどの相談に、いろいろな話を聞きながら対応していました。書店全体の構造や配置を感覚的に把握しているので、どこに何があるか的確に対応できるのです。今はコロナ禍で無人レジ化への流れになっていますけどね」(中嶋さん)
その一方、無人レジが広がれば広がるほど、コンシェルジュのような相談相手が求められるのではとも話した。





































