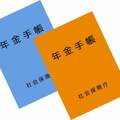小堀医師はこう述べる。
「この女性が本来迎えるはずだった101歳の老衰死と、現実に迎えることになった入院死という名の孤独死の格差は大きい。彼女にとっての“望ましい死”とは家族や主治医らに囲まれて自宅で迎えるはずだった10カ月前の死だったのではないかと」
これ以降、小堀医師は400人近い人々の臨終に関わったが、在宅看取りをおこなった割合は75%を超えている。
「闘病生活は長いので、ご本人やご家族との付き合いも長くなります。自然に、死ぬときはどうしたいかについても話し合うようになり、僕の考えも伝えられる。あくまで本人の意思が基本。それに家族の応援と、医者の後押し。それが在宅死のキーポイントになります。話し合っているうちにご家族が持っていたタブー視を変えることができると思えるようになりました」
もちろん、在宅死が善で、病院死が悪というわけではない。その家族にとっての最も望ましい死は何かを考えることが重要だ。
■事例5(89歳男性・間質性肺炎)
長男夫婦と3人暮らしをしていたが、夫婦は早朝から仕事に出かけ、日中は独居状態。体重の減少、食欲の減退が続き、デイサービスにも行かなくなったため、訪問診療が始まった。1カ月もすると傾眠状態の日が増え、長男夫婦は入院を望んだが、本人は「気楽に過ごしたいので入院はしたくない」と自宅療養を希望。2週間後に、帰宅した長男の妻が廊下で倒れている患者を発見。以降、寝たきり生活になる。長男夫婦が不在のときに、患者と2人だけで話し合い、「最期のときは短くても1~2週間、長ければ数カ月も続く。その間、長男夫婦が仕事を休むダメージは計り知れず、特に長男の妻が18年勤務している福祉施設は人手不足で介護休暇は無理」と説明すると、患者は「私は先生と嫁の言うとおりにする。どうせ長くは生きないし、向こうで母ちゃんも待っている」と入院を承諾。入院中に私は毎日患者のベッドを訪れたが、昏々と眠っており、最後まで言葉を交わすことはなかった。10日ほど過ぎたある朝、彼は静かに息を引き取った。