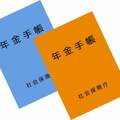■事例1(83歳男性・胆管がん)
妻と2人暮らしのこの男性は、病院で化学療法を行ったが効果が認められず、退院を勧められた。胸水・腹水がたまり、足のむくみもひどく、妻は在宅看取りを希望していた。しかし本人は「栄養をつけ元気になる」と入院を希望。自分の死を予感できず、入院時には退院後のスケジュール調整のために、妻にスマホを持ってくるように頼んだが、入院4日目に亡くなった。
死を認めたくない、自分が死ぬとは思ってもいない意識が、死を「タブー視」する気持ちにつながる。小堀医師は家族の死を恐怖する事例も目の当たりにした。
■事例2(80歳男性・前立腺がん)
前立腺がんは末期で骨にも転移しており、本人も介護する妻もその病状はしっかり認識している。患者は自宅で最期の時間を過ごす意思を表していたが、妻は「本人は自宅で逝くことを望んでいるが、私は家から死人を出したくない」と言明。その2週間後、大量の下痢を契機にして夫が傾眠傾向になると、妻は「正月明けまで家でみる」と言ったが、その2時間後「息子と話して、そんな状態ならすぐ入院させてほしい」と気持ちが変わり、緊急入院。男性はその1カ月後に死亡した。
本人や家族だけでなく、社会的な死へのタブー視も強い。
小堀医師は自分の母を自宅で看取っている。本人が病院は嫌だというのを尊重した。
「母は自分で新聞を取りに行ったときに玄関で倒れ、亡くなりました。するとご近所から『お医者さんのお宅なのに入院させなかった』と言われてしまったことがあります。やはり、死はネガティブな目で見られてしまうのだなと感じました」
もっと露骨な社会からのタブー視もあった。
■事例3(71歳男性・直腸がん)
手術不能の末期直腸がんと診断され入院。他の臓器への転移も見つかるが、本人の強い希望で退院し、訪問診療に切り替える。緩和ケアが奏功し、ADL(日常生活動作)が一時的に改善。しかし訪問診療後、待ち受けていたアパートの大家に「このアパートで死なれては困る。死ぬときは入院させるという約束でこの部屋を貸した」と主張された。そこで家族を同伴して家主と話し合いを重ねた結果、大家から「この部屋で息を引き取るのはやむを得ないが、ここから出棺するのは避けてほしい」と懇願され、遺体は寝台車にのせて搬送した。