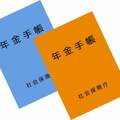小堀医師は言う。
「実は患者と2人きりで話しているとき、勤務中の長男の妻から私の携帯に電話がかかってきました。長男の妻は『今、義父と一緒にいるが、衰弱が激しいので明日にでも入院させてほしい』と嘘の電話をかけてきたんです。それほど追い詰められていたということですね」
小堀医師は、入院したことでこの患者は“人間らしい死”を迎えられたと思ったという。
こうして患者たちと接してきた小堀医師は、これまでタブー視されてきた死への意識が徐々に変わりつつあるとも感じている。
「ひとつはコロナで病院にお見舞いに行けなくなったこと。面会できないのは嫌なので、家にいてほしいという人が何人もいました。それと格差の問題もある。介護してくれる人がいない独居なので入院したいと思っても、お金に余裕がなく在宅死しか選べない人も増えています。そういう人にとっては病院のほうが安住の地になる可能性が高いのに」
さらに、約800万人といわれる団塊の世代が後期高齢者になる2025年問題への対応は、在宅医療の大きな課題になると指摘した。
「国は在宅診療を推進していますが、はたして高齢者の人口爆発を迎えたときに医師は気軽に在宅診療に応じてくれるのかというのが大きな問題になる」
06年に国は在宅療養支援診療所を創設し、診療報酬を高くした。これに予想を超える数の医療機関からの届け出があった。
「ところが、ちゃんと往診をしている在宅療養支援診療所は決して多くない。年間50人以上の在宅診療をしている診療所はわずか3%しかない。しかもその3%の医療機関が訪問診療全体の75%をカバーしているのが現状です。特に地方部での医師不足は深刻です」
中でも大きな課題は夜中に容体が急変したときだと小堀医師は指摘する。
「日中なら来てくれる医師も、夜中には電話をかけても出てくれない診療所が多くある。そこで仕方なく救急車を呼ぶことになるのですが、亡くなってしまった場合には救急車は対応できないので、警察マターになる。つまり、検視が行われる事態になってしまう。地域によっては病院外での死の約70%が検視となっており、これが是正されることが重要になってくると考えています。在宅での看取りの際には医者が来てくれないとどうにもならない。つまり鍵を握るのは医者の確保ということになるのですが、数が足りるだけではなく、患者それぞれが“かかりつけ医を持つこと”が大切になってきます」