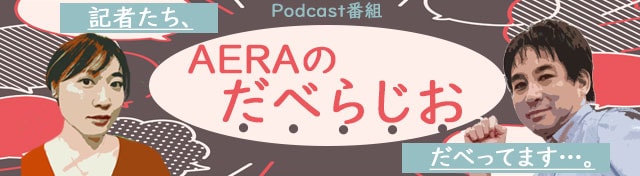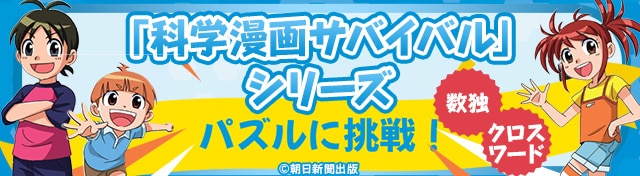ハーバード大の受験は「就活に近い」
「学生同士が互いをリスペクトし合っている雰囲気にはすごくひかれました。それは寮生活で寝食を共にし、夜遅くまで試験勉強したり、社会問題について議論したり、といった環境だからこそ培われる面が大きかったと思います。寮生活をしている大学の先生も含め、ずっと一緒にいて、『どっぷり学びに浸る』環境は魅力でした」
ハーバード大の入試にはどう取り組んだのか。
共通試験であるSAT(大学進学適性試験、日本の大学入学共通テストに相当)のほか、エッセイや課外活動、推薦状などで合否判定されるハーバード大の受験勉強は「就活に近い」イメージだった、と高島さんは振り返る。
「基礎的な英語の学力はもちろん重要ですが、それよりも『自分はどんな人間か』や『どんなことをしたいのか』といった自己分析能力が問われていると感じました」
ハーバードが求める学生とは
高島さんがハーバード大を受験した際、エッセイに「ハーバード大で受けた教育を、その後の自分の人生にどう生かしたいと考えているか」という設問があった。「なぜこの大学を志望したのか」ではなく、「大学での学びをどう生かしたいのか」という設問は強く印象に残ったという。
「『大学に入るのがゴール』という意識の人はハーバード大には求められていない、と実感しました」
日米の大学の違いについて、高島さんは「入学式と卒業式の比重の違い」に着目すると分かりやすいと説く。
「日本の大学では入学式にたくさんの人が集まる印象ですが、米国の大学では入学式は通過点にすぎないという認識のため、卒業式に圧倒的な比重が置かれています」
ハーバード大の入試面接の担当官は卒業生が務める。これにも「就活」を彷彿させる意図があるという。
「大学は学び舎である以上にコミュニティーの場ですから、この受験生を自分たちのコミュニティーに迎え入れたいかどうかは卒業生に判断させるのがいい、という観点から担当させているのかなと思います」
(AERA編集部・渡辺 豪)
こちらの記事もおすすめ 国内エリートから社会のリーダーは育つか 灘高、東大、ハーバード卒の芦屋市長28歳が「マイノリティーの経験」から得た気づき