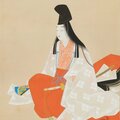こう前置いたうえで、機能する「指名委員会等設置会社」になることが先決だという。
「フジの再建の第一歩はガバナンスの再構築で、ガバナンスの一丁目一番地はトップ、最高権力者の選解任の機能であり、フジの根源問題もそこにあったのですから、まずやるべきことは指名委員会等設置会社になるべきです」
この指名委員会等設置会社は、社外取締役が過半数を占める指名委員会・報酬委員会・監査委員会の三つをもつ会社のことだ。
中でも重要なのは指名委員会で、取締役を選ぶのはこの委員会だ。
これまで日本の放送局、新聞社は、放送法・日刊新聞法という規制に守られた蛸壺だったために、社員がもちあがり取締役になり、社長になってきた。そのことに疑いをもつ人はおらず、いわば天動説の中で、物事を考えてきたと言える。
しかし、ちょっと考えればわかるように、かつての上司部下が社長と平取になるわけで、まず異論を唱えにくい。独裁者が出てきてずっと権力を保とうとすれば、代表取締役社長になった時点で、会社定款を変えて役員定年をなくしてしまう。
フジサンケイグループの鹿内家からの権力奪取は、1992年7月に産経新聞取締役会で、当時のグループ議長であった鹿内宏明の解任から始まるが、この解任を産経新聞内で日枝久と連動して企てた産経新聞社長の羽佐間重彰は当時64歳で役員定年が間近に迫っていた。失うものはなかったので、解任動議提出に踏み切ったのである。
ところが、日枝らが鹿内家から権力を奪取するとフジサンケイグループでは役員定年はなくなってしまう。
今回、第三者委員会の調査報告書で厳しく指摘されたのは、中居正広の案件にとどまらない。例えばプライムニュースキャスターの反町理を二人の女性社員がセクハラ・パワハラで会社に訴え、週刊誌報道されたにもかかわらず、日枝と政界をつなぐ反町は、執行役員・取締役と逆に出世していく──というような企業風土は、そうしたガバナンスの帰結だったのだ。
30日のFMHの発表にも「26年6月の指名委員会等設置会社への移行を検討します」とはある。が、注意してほしい。これは25年6月ではなく、なぜか一年後の26年6月。しかも「実行する」ではなく、「検討する」なのだ。