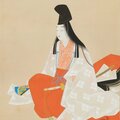フジテレビで今回の問題に対処している若手のチームは優秀だ。
世論を敏感にとりいれ、役員の中の女性比率3割、平均年齢71歳超えだった取締役の若返り、すべて丸飲みにして、6月の株主総会にむけた取締役候補選任決議案等を出してきた。
4月30日には、日枝久の最後の直系部下とされたフジ・メディア・ホールディングス(FMH)代表取締役社長の金光修の6月の株主総会をもっての退任、「フジ・メディア・ホールディングス グループ改革に向けて」も発表した。
フジテレビ問題が起こる前の取締役で、残るはアニメ畑出身の清水賢治ひとりとなった。
にもかかわらず、4月30日以降も株価は週末まで下げ続けた。
この意味するところは何か?
「JAL再生タスクフォース」のサブリーダーとして当時の稲盛和夫会長とともに、日本航空を見事に再建したプロ経営者の冨山和彦(現IGPIグループ会長)に聞いてみた。
社員が社長になる その常識をまず疑え
冨山は、もともとボストン・コンサルティング・グループの出身、政府の要請で、2003年4月に産業再生機構の設立に参加、代表取締役専務兼業務執行最高責任者(COO)を務めた。
旧日航の場合、会社更生法を申請し、旧株主がもっていた株は100パーセント減資つまり紙屑になったわけだから、「経営者はもちろん取締役は全員交代が原則でした。経営継続上、やむを得ず誰かに残ってもらう可能性はゼロではありませんが、産業再生機構案件では例外はなかったと記憶します。JALは会社更生法を使ってますからやはり全員退任です」(冨山)。
「フジの場合はまだ破綻はしていないので同列に論じるのは難しいですが、第三者委員会の報告書に素直に従うならば、問題の根源としてガバナンスがまったく機能していなかった、すなわち取締役会が機能していなかったのですから従来の取締役は原則として適格性を失うとみなされるのが自然でしょう。そこは清水氏ももともと取締役であったなら同じでひとまず失格でしょう」
「ただ、経営の継続性という観点からは暫定的に誰かに経営させる必要もあるので、その限りにおいて清水氏が適任ならば暫定的にやらせる選択は無くもないです、ある種の管財人的に」