
子どもの頃は着物嫌い 中学からサッカー漬けに
弘明は「業界の常識は一般の非常識」を胸に、他の呉服店との差別化を図ってきた。病院のカルテのように「着物カルテ」を作成し、客が購入した品物や家族構成、話した内容などをすべて記録する。また、一般的な呉服屋では、店頭の反物価格に仕立て代は入っておらず、合計金額が不明瞭な時代だったが、いち早く仕立て代込みの価格を提示した。2002年には男の着物の専門店を立ち上げ、和裁にはなかった仮縫い制度を導入した。
常に大事にしてきたのは、産地まで足を運び、職人たちと会うこと。当時は呉服屋が直接、着物職人に会いに行くことはまずなかったが、職人に会い、どんな人が作ったのか、作品の持つ特性はどういうものか、どんな思いで作ったのかを聞いた。そしてその着物の持つストーリーを伝えること、「伝える職人」になることを徹底してきた。
そんな父を持つ泉二は、今でこそ毎日のように着物を着るが、子どもの頃は、「古い。かっこ悪い」と着物が嫌いだった。父は家族旅行でもレストランでも学校行事でも、365日、着物姿。「お前のおやじ、また着物を着ているよ」などと友達に言われることもあり、それがまた嫌だった。
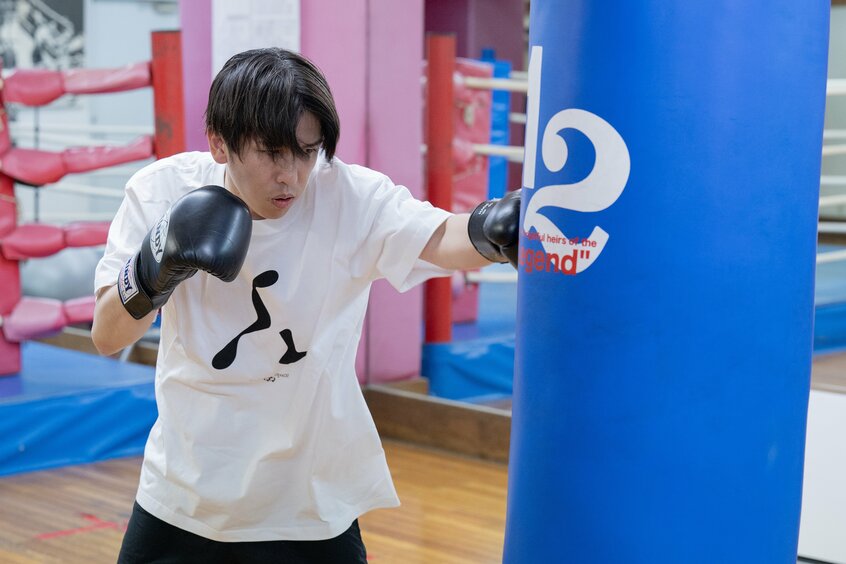
中学、高校はサッカーにのめりこんだ。朝練に始まり授業が終われば部活。部活が終わって、近くの東京大学のグラウンドで21時ぐらいまで練習することもあった。高校3年間の担任だった石田正人(58)は言う。
「勉強しろと言っても何を言っても、朝から晩までサッカー。そこについては一本、筋が通っていたかな(笑)」
泉二のコミュニケーション能力は抜群で、石田はクラスをまとめるために、泉二を頼った。
「中学、高校一貫校の男子校で、啓太が進学した国際高校の方は学年で1クラスしかありませんでした。中学校から上がってきた生徒は比較的穏やかな子が多かったけど、高校から入った生徒はやんちゃな子が多かった。ケンカなんて日常茶飯事。彼はそんな子たちとも誰とでも仲良くできる性格でした。ケンカをしていないか、私が叱った子が今、何を考えているか、情報を集めるために誰に聞けばいいかと考えたときに彼が適任でした」
ただ、泉二も反抗期。授業中に漫画を読んだり、風紀委員につかまったり……。他の先生に叱られるたびに、石田が「いい加減にしろ」と連れ戻しに来てくれた。
「当時は反抗しているつもりはなかったんですよね。石田先生がいなかったら、卒業できていなかった。先生のおかげです」(泉二)





































