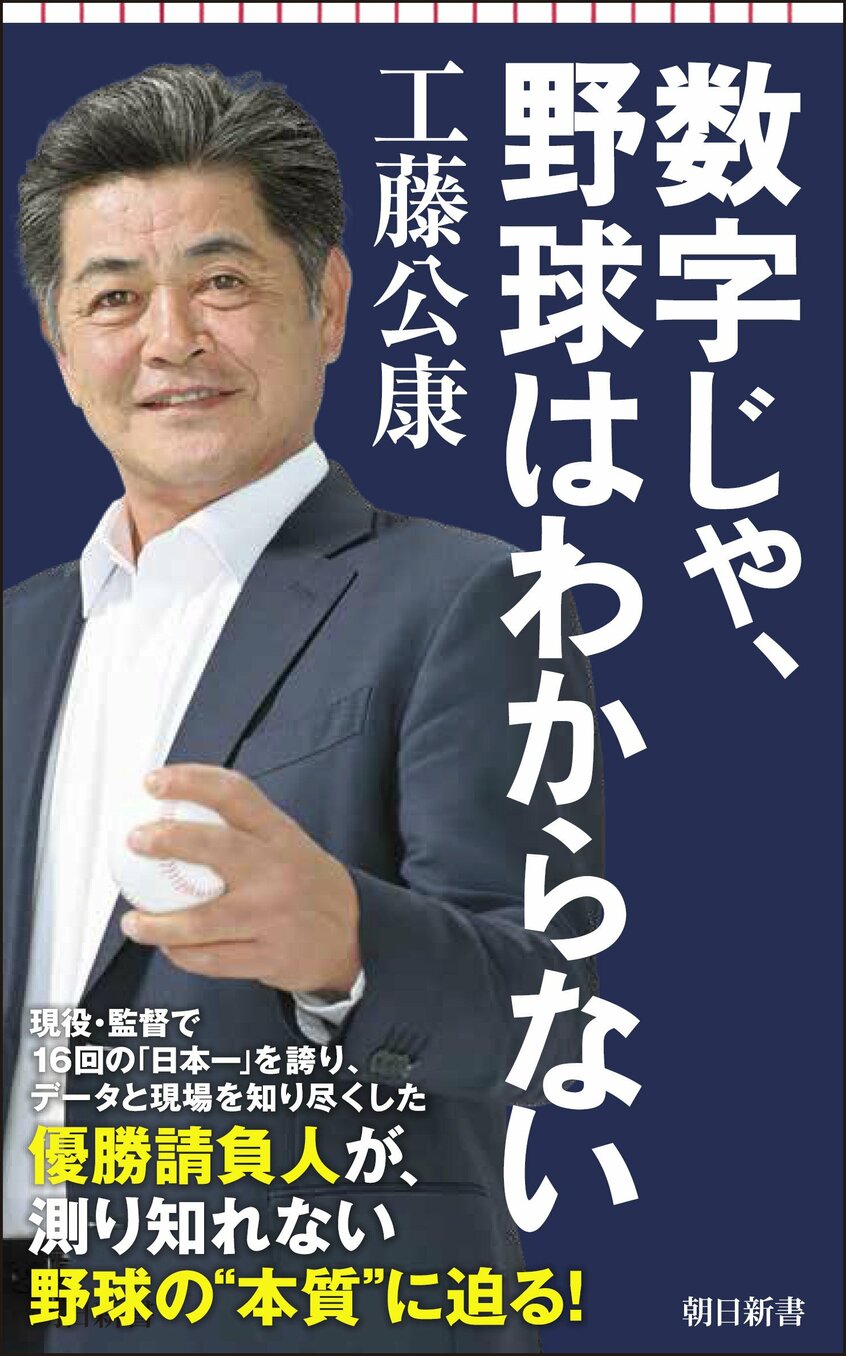
あるいは、野球ファンであれば、ピッチング理論やバッティング理論の変化も見聞きしているはずだ。わかりやすいのは「フライボール革命」だろう。一般的には、ダウンスイングでゴロを打つよりも、アッパースイングでフライを打ったほうがヒットの確率は上がる、という理論と理解されていると思う。
フライボール革命のように、昭和の野球で「常識」とされていた理論が「間違った技術」で、令和の新しい理論のほうが「正しい技術」と思っている野球ファンも多いのではないだろうか。
また、「2番打者最強説」というのもある。昔はバントやエンドランなど「小技」ができる打者を2番に置くのが常識的な戦術だったが、今は大リーグの影響もあって、2番に強打者を置く戦術も多くなっている。
データや理論、戦術にしても、その影響によって野球が変化しているとして、それを単純に進化と呼べるかどうか。なかなか難しい問題だ。
体格は変わったのか?昭和と令和の選手を比較
野球ファンならもっとわかりやすい変化を感じていると思う。たとえば、「昭和の選手に比べて令和の選手のほうが体が大きくなった」と感じる人は多いのではないか。私自身、プロ野球選手に限らず、野球教室で小学生を見るたび、「最近の子は体が大きくなっているな」と感じている。
数値の変化を見てみよう。2024年のプロ野球選手の平均身長は180.8センチ、平均体重は85.8キロ。平均身長は私が西武ライオンズに入団した1981年には、すでに180センチを超えていた。つまり、40年以上前から横ばいだ。一方、平均体重のほうは当時75キロ超だったから、今に比べて10キロほど細かったことは間違いない(24年の数字は編集部調べ、81年の数字は「日本人プロ野球選手の体格の推移〈1950〜2002〉」中山悌一、「体力科学」53〈4〉、443~453、2004年、一般社団法人日本体力医学会から)。




































