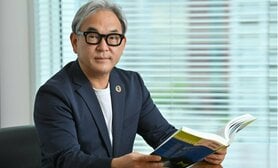一方で、日本のZ世代には未来を悲観する傾向も感じられるという。
「そんな子たちにとっては人生に終わりがあることが唯一の希望で、自分の最期をファッションのように捉え、死を自己表現の場と考えているのではないでしょうか」
死に投げやりな高齢者
村田さん自身、20代に転機があった。28歳の時に母親が亡くなり、その後、祖父母も相次いで亡くし、急に死が近づいたことが葬送業界にかかわるきっかけになった。
「私は身内を亡くしたことで自分ごとになりましたが、今の若い世代にとって身内の死はそれほど自分ごとにはなっていない感じがします」
どういうことか。死は一人称、二人称、三人称に分かれる、と村田さんは言う。
「私が死と向き合ったのは二人称、遺族の立場ですが、今の若い世代の関心は『あなたの死』や『あの人の死』ではなく、一人称の『私の死』なんです」
村田さんは自治体の終活セミナーなどで全国の高齢者と接する機会が多い。そのとき感じるのが高齢者の「自分の死」に対するこだわりのなさ、悪く言えば投げやりな態度だという。
「坊さんも呼ぶな」「戒名もいらない」「ただ焼いてその辺に撒いてくれればいい」
村田さんはこう指摘する。
「自分の意思をはっきり示さないのは日本人の特性かもしれませんが、死は残された人のものだから、自分の意思なんてどうでもいい、と考えている人がほとんどです」
死とどう向き合えばいいのか。村田さんは若い世代には「そんなに頑張らなくていい、と言ってあげたい」と話す一方、高齢者には「若い人たちが人生に希望を感じられるよう、もっと楽しそうに生をまっとうしていく姿を見せてほしい」と訴える。
「『葬式なんてやらなくていい』と話すお年寄りは、長生きしても幸せではない、というメッセージを周囲に発しているのと同じです。そんなネガティブな後ろ姿が若い世代の希望を失わせているんですよ、と伝えたいです」
(編集部・渡辺豪)
※AERA 2024年12月2日号より抜粋・加筆