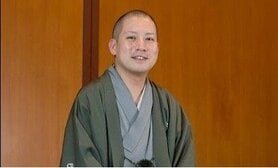津波を実況した閖上の地 罪悪感を抱え悩み続けた
あの瞬間から、武田いわく「声を枯らしながら」震災の報道は続いた。情報は瞬時に伝えた。太平洋沿岸の港に設置されたカメラも正常に作動していた。でも、2万人以上が犠牲となった事実。地震発生から津波到達までの時間に、自分たちがやれることがあったのではないか。彼は苦悩し、そして罪悪感を抱えていた。
「自分が放送席に座って最初に実況した映像が、ここでした。そこからずっと、NHKはすべての番組を飛ばし、僕も日中担当したんですけど、あんまり覚えていないんです。空(むな)しくて、悲しくて。いまだに(その思いが)あります」
妻の陽子も当時を振り返る。陽子はあの日、外出しており、彼の津波の実況を直接は観ていない。
「あの実況をしたと知り、『本当にあれをやったのか』って。すごくつらくて。彼自身、声も喉も痛めたし、それ以上に心を病んだと思います。眠れないし、でも使命感でやってきて。臨時態勢の時からずっと、『もっとやることがあったんじゃないか』『僕ら、できていないんじゃないか』って、悩み続けていたようです」
2018年2月、現地の取材を続けるプロデューサーに促され、武田は初めて閖上の地を訪れた。亡くなった閖上中学校の生徒を悼む慰霊碑の社務所としてつくられた、津波復興祈念資料館「閖上の記憶」へ。この時から武田は頻繁にこの場所を訪れるようになり、家族を亡くした語り部たちと、あの日のことについて語るようになった。
「何でしょうね、この時期になると、ここに来たくなるんですよ」
逃げ場として来ているわけではない。東京にいると「自分は何もしていない。何も役立っていない」と、今でも自らを責める気持ちが湧き上がる。そんな気持ちを抱えながら閖上に来ると、むしろ「逃げてはいけない」と、原点に立ち返る思いになる。閖上の語り部は、こんな言葉を一人ひとりにかける。
「悲しみによって繋(つな)がる人たちがいてもいい」
切迫性をどう表現するか 今伝えるべき言葉を考える
2024年1月1日、午後4時10分。能登半島地震。その数分後、「大津波警報」が発令された瞬間、NHKアナウンサーの声は、およそ聞いたことのない厳しい口調に変わった。
「今すぐ可能な限り、高いところへ逃げること!」
「決して、立ち止まったり引き返したりしないこと!」
これは、NHK在局時の武田が中心となってつくった、報道マニュアルにそったものだ。