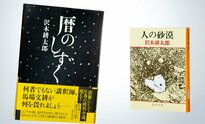「不十分な中でも生きていけるリズムはできてきました。でも、避難生活がいつまで続くかわからないし、仮設住宅に入ってもあくまで仮住まいです。『落ち着いた』と言えるのは何年も先になるんじゃないかと思います」
支援団体「災害NGO結」代表の前原土武さんは、「能登の復興は始まる前に終わるかもしれない」として、こう懸念する。
「東日本大震災のときも、熊本地震のときも、『被災地を支援しよう』というムーブメントがありました。一方、今回は発災直後にボランティアの自粛が強く呼びかけられるなど、その機運がありません。まだ水道が復旧していない地区もありますし、がれきの撤去もこれからです。ただ、報道も減って被災地の外では既に過去のことのような空気があります。これから災害関連死の問題などが本格化する時期ですが、被災している方々は支援の手を感じられていない。命を救うための活動は今が正念場だと思っています」
重機チームの活動も
前原さんら災害NGO結は、奥能登の玄関口・七尾市に拠点を構える。市から拠点として借り受けた旧西岸小学校の校舎前に「広域支援ベース@にしぎし」と大書した看板を置いているように、その活動範囲は広い。七尾市内はもちろん、穴水、能登、珠洲、輪島まで被災各市町で支援物資の配送、炊き出し、重機作業などの活動を行っている。ここを拠点に活動するのはスタッフやボランティアら1日約25~50人。災害NGO結の代表として、各活動のコーディネートや他団体との調整などを行うのが前原さんだ。活動で重視しているのは、「支援の穴」をふさぐことだという。
例えば、重機支援などを得意とする技術系NPOは多くが珠洲市で活動する。昨年5月にあった最大震度6強の地震の際にも被害の大きかった珠洲に入っており、今回も現地から直接依頼を受けるなどしたケースが多いからだ。ほかの市町でもいくつかの技術系団体が活動するものの、市街地からの道路が不通になるなどして支援の手が届きづらい地区がある。災害NGO結の重機チームが活動するのはそうした支援の薄い地区だ。また、民間団体による炊き出しも細り始めていることから、食事の支援も強化しているという。