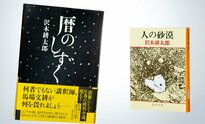目指すのはやはり、関連死をなくすことだという。代表の中島武志さんは言う。
「例えば、避難所から家に戻った住民さんは何から手を付けていいかわからずに絶望します。片付けの道筋を示すことができれば少しは希望を持てるかもしれない。仮設住宅への移転が始まると孤立防止の寄り添いなども必要になってきます。被災後はそれぞれのフェーズであらゆる『心配ごと』が出てきます。『生きててもしゃあないわ』と思わないように不安を一つずつ減らしていくのが、今できる僕らの役割だと思っています」
輪島市や能登町でもまた、多くの支援者たちが汗を流している。「コミサポひろしま」の小玉幸浩さんは連日、輪島市の被災家屋からの家財取り出しに取り組んできた。場所にめどを付けながら重機やチェーンソーを駆使し、貴重品や思い出の品を捜していく。2月には、倒壊ビルから携帯電話、時計、ピアスなどを取り出し、オーナーに手渡した。亡くなった家族のものだったという。
「ご家族を亡くした方や、家を失ってしまった方に、ひとつでも大切なものを返してあげたい。その一心です」
発災当初から遅れが指摘される能登半島の復旧活動。過去の被災地と比べ、様々な問題が目立つのも事実だ。災害ボランティアセンターが受け入れる一般のボランティアは、発災2カ月以上が過ぎた今月5日時点で延べ7千人余り。発災2カ月で20万人以上が活動した東日本大震災などよりケタ違いに少ない。2カ月以上たったいまも十分に食事が届かない避難所がある。それでも、それぞれの場所で今できることに懸命に取り組む支援者たちがいた。(編集部・川口穣)
※AERA 2024年4月1日号