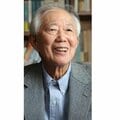一方、1887年(明治20年)に書かれた『三酔人経綸問答』の生き生きとした筆致はどうだ。当時の政治思想の迷走が、そのまま、滋味あふれる豊かな日本語で綴られている。
『三酔人経綸問答』は題名の通り、三人の酔っぱらいが国家を論じる体裁で進んでいく。国権主義を代表し海外進出を主張する豪傑君。理想論的な民主主義論、非戦論を唱える洋学紳士。そしてそれを、当時の日本の現状に合わせ、現実的に調停しようと試みる南海先生。
いずれにも中江兆民の姿が偏在し、その苦悩が対話の端々にうかがえる。明治の文学青年たちが、内面だ言文一致だと右往左往していた頃に、政治の世界でこれだけの文学性を持った作品が生まれていたことは驚嘆に値する。
且つ世の所謂民権なる者は、自ら二種有り。英仏の民権は恢復的の民権なり。下より進みて之を取りし者なり。世又一種恩賜的の民権と称す可き者有り。上より恵みて之を与うる者なり。恢復的の民権は下より進取するが故に、其の分量の多寡は、我の随意に定むる所なり。恩賜的の民権は上より恵与するが故に、其の分量の多寡は、我の得て定むる所に非ざるなり。若し恩賜的の民権を得て、直ちに変じて恢復的の民権と為さんと欲するが如きは、豈事理の序ならん哉。
このくだりは有名な、革命によって獲得した「恢復的な民権」と、政府の裁量の範囲で与えられた「恩賜的な民権」の違いについて述べた箇所だ。