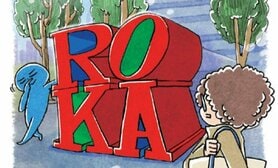就職には何の魅力もない 「まれびとハウス」が話題に
そこで小野が見たものは、日本の社会の皮肉な実相だった。メガバンクの元頭取という常連男性は、新人の女の子を隣に座らせては15分程自分の手を揉(も)ませ、チップとして1万円を払っていた。
「金銭感覚がバグりますよね。銀座の店で働いて、世の中って本当にくだらないなと思いました」
店にはその人物と同じような一流企業の役員の男性が複数、毎日のように来ては湯水のように金を使っていた。男たちの目は一様に死んでいた。酒に酔って「俺は偉い」と威張る男たちを内心でホステスたちは馬鹿(ばか)にしていた。政治家一族に生まれた有名な議員がひどいセクハラをする姿も目の当たりにした。そういう客の隣には決まって置物のように静かなカバン持ちの部下がいた。
「問題はなぜその人たちが毎日一人で銀座に来るかですよ。結局、会社にも家にも居場所がない、本当に寂しい人たちだなと感じました」
自分も大学を卒業して企業に就職すれば、このヒエラルキーの一番下に入ることになる。何十年も頑張って働いて出世した末の「あがり」がこの場で「置物」になることなのか? そう思うと、就職すること自体に何の魅力も感じなくなった。
「女性の場合、この国では社会のトップを目指すというレールにすら乗れない。男のように働いて“名誉男性”になるか、女として男性のヨイショ役になるか。どちらの道もうんざりでした」
だが社会に出た後に、何をすべきか見当がつかない。小野も周囲の学生に流されるまま、就職活動に取り組んだ。ある日、最終選考先の企業が入る東京・丸の内のビルに向かう途中、なぜか涙が止まらなくなった。小野はその場で面接担当者に「すみません、行けなくなりました」と電話し、就職からドロップアウトした。
「表面を取り繕うのは上手いので、面接はいいところまで進むんです。でも本当はまったく就職したくないから、体が悲鳴を上げたんです」
開花した作家としての才能 シェアハウスで子育て
大学を出た小野は就職せず、インターンで知り合った学生たち6人とともに田端のシェアハウスで暮らし始めた。「まれびとハウス」と名付けられたその4LDKのマンションには数カ月で1千人を超える若者が来訪し、マスコミにも取り上げられた。小野はそこでトークイベントや勉強会を企画し、同時に新宿・歌舞伎町にあるバー「漆黒」でアルバイトをして生活費を賄うようになった。
(文中敬称略)(文・大越裕)
※記事の続きはAERA 2023年10月23日号でご覧いただけます